|
高校の教科書が変わる
「探究学習」を重視
2021.4.1/2022.11.5
高校教科書「探究」重視
新科目 課題解決の力育む 朝日新聞 2021(令和3)年3月31日(1面)
2022年度から使われる高校の教科書が、課題を調べて考える「探究学習」を重視した内容に変わる。文部科学省が30日、検定を終えたと発表した。同年度から9年ぶりに新しくなる学習指導要領に基づくもので、新科目「歴史総合」や「公共」などの教科書も公表された。検定では、北方領土や尖閣諸島など領土関連の記述に厳格なチェックが入った。
22年度から学校で教える内容の基準を定めた学習指導要領が新しくなり、数学や理科の考え方を身につける教科「理数」が新設される。「地理歴史」は、近現代の世界史と日本史を関連付けて学ぶ新科目「歴史総合」や、防災なども学ぶ新科目「地理総合」が必履修となる。科目の見直しに伴い教科書も変わり、資料や図が多用さている
多くの教科書で新たに盛り込まれたのが探究学習だ。自分で課題を見つけ、情報収集し、分析し、表現する学習方法で、知識偏重を脱し課題解決の力を育むねらいがある。「理数探究基礎」など科目名にも盛り込まれた。今年から始まった大学入学共通テストでも同様に思考力などを問う傾向が強くなり、文科省は「生徒に身につけて欲しい力が教科書でも同じように重視された」とみる。
例えば、「現代社会」から衣替えした新科目「公共」では、ほとんどの教科書が、持続可能な開発目標(SDGs)などをテーマに、課題設定から表現までの探究学習の手順を一つの章を使って紹介。英語では世界のリーダーを取り上げ討論する学習を促す事例がある。
(伊藤和行、堀之内健史)
視/点 教員の指導力がカギ
検定結果が公表された高校の教科書には「探究学習」のコーナーがちりばめられている。問いを立てて調べ、表現する学びだ。
「教科書の設計図」である学習指導要領が力点を置き、大学共通テストも探究学習の場面を問題文に織り込んでいる。「一方通行」と批判されてきた高校の授業を変える狙いだ。
探究学習が根付くかどうかのカギを握るのは教員である。だが、現場の状況は厳しい。「情報」は教科の免許のない教員も教えている。「地理」も専門の教員が少ない。探究学習以前に、そもそも教えられるかが問題になってる。
教員を取り巻く環境も深刻だ。ベテランの大量退職の波が押し寄せるなか、働き方改革は道半ば。多忙で授業準備もままならない。
大学の教員養成も、新科目の内容や教え方に追いついているとは言いがたい。新教科書を使った授業が始まるまで1年しかない。文部科学省や教育委員会は、探究学習を指導できる専門的な教員をどこまで増やせるかが問われる。
(編集委員・氏岡真弓)
2022年度からの高校教科書 こう変わる 朝日新聞をもとに作成
◆課題解決型の「探究学習」が盛り込まれる
◆世界史と日本史を統合した「歴史総合」、自然災害などを学ぶ「地理総合」などの新科目が登場
◆人間と社会を考える「公共」や、プログラミングなどを学ぶ「情報Ⅰ」が全員が学ぶ科目に
◆教科「理数」が新設され、「理数探究基礎」が登場
◆北方領土や竹島、尖閣諸島が「固有の領土」であることの記述が学習指導要領で求められる
◆QRコードの活用が広がる |
新必修科目 教えやすく 時時刻刻
免許持たない教員意識 図説を多用 朝日新聞 2021(令和3)年3月31日(2面)
情報や地理総合など新たに全員が学ぶことになる科目では、教え方に不安を抱く教員への配慮がにじんだ。一方、北方領土や竹島、尖閣諸島など領土関連では、政府見解を細かく紹介する記述が目立った。
専門教員配置求める声も
新たに必履修になった科目は、その科目の免許がない教員も教える可能性が高い。こうした「免許外教科担任」を自治体が許可した件数は、2016年度で3760件にのぼった。
このうち3分の1を占める情報科では、数学や理科、保健体育など他教科の免許を持つ教員が教える高校も少なくない。「情報Ⅰ」は高校3年間で2単位しかなく、地方の小規模な高校では、専門の教員を配置できない現実がある。
情報Ⅰでは、プログラミングや情報デザイン、データ活用など、専門的な分野も扱う。検定を通った教科書をみると、免許外の教員も教えることを意識して作られたことがうかがえる。
情報は、25年以降の大学入学共通テストで出題される方向で検討が進む。情報科に詳しい電気通信大学の中山泰一教授は「免許外の教員が教えたり、他教科とあわせて教えたりすることが当たり前になっていることが、根本的な問題。情報教育が求められ、入試科目にも入る時代にこれでいいのか」と、専門性のある教員配置を求める。
「地理総合」も新たに全員が学ぶ科目になり、同様の課題を抱える。これまでも必修だった世界史と比べ、地理を専門に教える先生は少ない。ある出版社の担当者は「高度な内容の記述はできるだけ避けるようにした。地理専門の先生でなくても教えられるよう工夫した」と打ち明ける。
授業の進め方や成績評価の案をつくって提出する出版社もあった。「四半世紀前だったら『そんなものいらない』といわれたが、いまは歓迎される。新しく必修となる科目では需要が高い」(担当者)という。
(宮坂麻子、阿部朋美、土屋亮)
北方領土・尖閣 細かい意見 「ロシア実効支配」→「不法占拠」
日本の領土をめぐる表現は適切か――。新設科目の「地理総合」や「歴史総合」、「公共」の検定ではこの点が注視された。
北方領土については、2018年改訂の学習指導要領の本文に「領土」を扱うことが新たに盛り込まれたためだ。背景には、第1次安倍政権の06年に教育基本法が改正され、「我が国と郷土を愛する態度を養う」が教育の目標の一つとされたことがある。
一方、北方領土の返還交渉に力を入れた第2次安倍政権は「ロシアによる不法占拠」という政府見解は堅持しつつ、前面に出すのを控えた。文部省幹部は「ときの政治情勢で様々な考え方が出る」とした上で、「指導要領に基づく教科書は、政府の基本的な考えを知ってもらうことが大切」と話す。
また、多様な見方や議論が重視される公共でも、尖閣諸島をめぐる領土問題はないという政府見解に基づく検定意見がついた。文科省は「わが国の立場を正確に理解したうえで議論しないと、対等に議論できない」と理由を説明する。
立正大学の浪本勝年名誉教授(教育法)は「日本政府の見解を一方的に載せていては、生徒は思考停止に陥りかねない」と話す。「尖閣諸島をめぐり領土問題が存在しない」と教科書に書いても、現実には日中が衝突しかねない場面があると指摘。「学習指導要領自体、多面的・多角的に考えるようにも促している。生徒には相手国の主張や問題の判断材料を示して考えさせるべきだ」と語る。
(伊藤和行、杉原里美、編集委員・氏岡真弓)
北方領土に関する記述はこう変わった 朝日新聞をもとに作成
| |
原 文 |
修正文 |
| 地理総合 |
北方領土は現在も事実上ロシアによって統治されている |
北方領土は現在もロシアによる不法占拠が続いている |
| 日本の領土である竹島は |
日本固有の領土である竹島は |
| 歴史総合 |
北方領土は、現在までロシアが実効支配を続けており |
北方領土は、現在までロシアが不法占拠を続けており |
公共 |
1956年の日ソ共同宣言で、歯舞、色丹の2島を平和条約締結後に、日本に返還することで合意したが、いまだ実現していない |
1956年の日ソ共同宣言で、歯舞、色丹の2島を平和条約締結後に、日本に引き渡すとされていた |
自らに引き寄せ テーマ深掘り
来春からの高校教科書 検定結果 朝日新聞 2021(令和3)年3月31日(25面)
来春から使われる高校教科書の検定結果が公表された。新学習指導要領の全面実施に伴い、教科・科目が再編されて初めての教科書は、テーマを深く掘り下げる「探究」や、学びと生活との結びつきを重視するものが目立つ。各教科・科目の特徴を紹介する。
エネルギー・防災 よりよい選択とは
地理総合
「地理総合」は、地理として約50年ぶりに必履修となった科目だ。地図や地理情報システム(GIS)を使って世界をとらえ、領土も学習する。生活文化の多様性や国際協力の重要性、災害、防災、についても学ぶ。5社の6点が合格した。
近現代の世界と日本 多角的に学ぶ
歴史総合
「歴史総合」は近現代史に特化し、日本史と世界史を関連づけて学ぶ。暗記するだけの受け身の学習から、多面的・多角的に考え発信する主体的な学びへの転換を目指す。「近代化」「国際秩序の変化や大衆化」「グローバル化」の3テーマを設け、資料を活用し歴史の学び方も身につける。7社12点が合格した。
公共 正義とは 答のない問い
公民科では、現代社会が廃止され、「公共」が新設された。8社12点が合格し、現代的なテーマを通して「正義」「公正」「幸福」など答えのない課題を考えさせる教材が目立つ。
情報Ⅰ プログラミング 全員対象
情報科は、これまでの情報の収集や表現について学ぶ「社会と情報」、パソコンを使ってプログラミングを学ぶ「情報の科学」のいずれかを選択する必履修科目だった。今回から全生徒が学ぶ「情報Ⅰ」が新設。さらに学びを深める選択科目として「情報Ⅱ」ができた。
情報Ⅰの新設により、これまで一部の生徒しか高校で学ばなかったプログラミングを全生徒が学ぶことになり、各教科書会社は、生徒が小中学校で学ぶ内容にばらつきがあり、この教科の免許を持たない教員が教えている場合も多いため、「わかりやすい教科書をつくることに苦心した」と口をそろえた。
検定に通った「情報Ⅰ」は、6社12点。情報社会の問題解決▷コミュニケーションと情報デザイン▷コンピュータとプログラミング▷情報通信とネットワークとデータの活用、の4領域をバランスよく扱った。
どの社も高校生にとって身近なSNSの使い方に言及。炎上や誹謗中傷のリスク、つながった相手とのトラブルなど、SNSと上手に付き合う方法が紹介されていた。
理数探究基礎 課題設定から発表まで
理科や数学を活用し、多角的に考える力を養う新設の選択科目「理数探究基礎」は2社2点が検定に通った。大学進学を見据えた人が主な対象で、幅広い分野から探究の課題を見つけ、手法を学ぶ。
国語 履歴書やメールの書き方も
評論文を扱う現代の国語と、小説・随筆・詩歌と古文・漢文を合わせた言語文化の2科目で、9社の34点が合格した。
現代の国語では「実社会に必要な知識や技能を身に付ける」という新学習指導要領の方針を受け、実用的な教材が目立つ。
言語文化では、日本の言語文化への理解を深めることが重視された。
数学 仕事の現場での活用例を示す
数学は5社48点が合格。日常生活や社会とのつながりを意識した内容が目立つ。「身近にある数学」を題材にしたコラムも多かった。理系教科ながら、日本文化に親しみを持たせる工夫も。江戸時代の和算や三角測量、着物の和柄などを複数の社が取り上げた。
理科 身近な疑問から法則考える
理科は5社43点が合格した。身近なものへの疑問から出発して理論や法則を学ぶ構成が目立った。学びが卒業後も役に立つと感じてもらえるよう、理科の知識を生かして企業で働く人を紹介した教科書も多く、日本人科学者の成果についての記述も増えた。
英語 場面想定 アウトプット強化
英語コミュニケーションと論理・表現の2科目で、13社42点が合格。新学習指導要領では、聞く、読む、話す(やり取り・発表)、書く、の4技能5領域の目標を設定。各社とも、読んだり聞いたりした内容を自分なりの言葉で話すリテリングや、プレゼンテーションなど、アウトプットの機会を豊富にした。
保健体育 健康・安全 今の課題盛る
保健体育は2社3点が合格。個人や社会生活における健康や安全について理解する狙いから、今日的な問題を多く載せた。仕事と健康を考えるために働き方改革を掲載。五輪・パラリンピックの課題を特集したページも見られた。
家庭 SDGs・ジェンダー充実
家庭は6社16点が合格。新学習指導要領では持続可能な社会が明示され、SDGs(持続可能な開発目標)を各社が冒頭で扱ったほか、プラスチックごみの問題やフェアトレード(公正な貿易)などを紹介した。
2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられるのを見据え、契約の重要性や消費者保護の内容も充実。LGBT(性的少数者)やデートDVなどジェンダーの視点からの記述も手厚くなった。
芸術 音楽の著作権 全社が触れる
音楽は3社4点が合格。新学習指導要領では生活や社会の中の音や音楽、音楽文化と関わる資質・能力の育成が打ち出され、郷土の民謡、外国語の歌曲、世界の諸民族の楽器など多様な音楽を取り上げた。音楽に関わる著作権は全社が触れ、許可が必要かどうかを考えさせている。
美術は2社3点。ここでも生活や社会の中の美術や美術文化がうたわれ、浮世絵、漫画表現、スプーンのデザイン、現代アートなど幅広く掲載。
書道は4社4点が検定に通った。日本と中国それぞれの書を中心に、文豪の直筆原稿など多彩な書を紹介している。
工芸は1社1点が合格した。
(阿部明美、石平道典、川村貴大、木下こゆる、小宮山亮磨、杉原里美、土屋亮、西村悠輔、堀之内健史、三島あずさ、宮坂麻子、宮崎亮、編集委員・氏岡真弓)
「情報」教員796人正規免許なし
文科省調査 公立高全体の17% 朝日新聞 2022(令和4)年11月9日
全国の高校で、教科「情報」の正規免許を持たずに情報の授業を担当している教員の数が、今年5月1日時点で計796人だったことが8日、文部科学省の調査でわかった。情報担当教員全体の17%にあたる。情報は専門の教員が配置できていない地域があり、教える態勢の格差が指摘されてきた。文科省は、態勢強化に向けた策を続々と打ち出している。
前回調査よりは改善
高校の新学習指導要領(今年度の高1から適用)に基づき、情報はプログラミングやデータ活用などを学ぶ「情報Ⅰ」(全員が履修する科目)と発展的な「情報Ⅱ」(選択科目)に再編され、情報Ⅰの授業が始まっている高校もある。
こうしたなか、文科省は都道府県と政令指定都市を対象に、公立高での情報担当者教員の配置状況を調査。その結果、担当教員計4756人のうち、情報の正規免許を持たず別の教科の免許を持つ人が教える「免許外教科担任」は560人、正規免許を持つ教員を採用できないときに期限付きで発行される「臨時免許状」を持つ教員は236人。合わせて796人が情報の正規免許のない教員だった。
20年度実施の前回調査では全体(5072人)の24%を占めたが、今回は17%。「免許外」が20年度比417人減、「臨時免許状」は同20人減となった。
態勢強化へ国、改善計画を要請
情報Ⅰが初めて出題される25年の共通テストまで2年余り。来年度から発展的な選択科目の情報Ⅱも始まる。だが、一部の自治体は情報の正規免許を持つ教員を十分に確保できておらず、文科省は改善を自治体に迫っている。
20年度の調査では、情報担当教員の24%にあたる1200人余りが情報の正規免許を持たずに授業を担当していたことが判明。それ以降4月まで3度にわたって改善を促す通知を各教委に発出してきた。
今回の調査では、情報の正規免許を持たない教員の比率が17%に改善したが、それでも公立高を設置する計65の都道府県・政令指定都市のうち49自治体で、正規免許のない教員が授業を担当する学校があった。
文科省はより強い指導が必要だと判断。これらの自治体の教委に改善計画の策定を要請し、免許保有者が複数校で指導する態勢を強化▷教員免許を持っていない専門知識のある人への特別免許状の交付増▷情報科教員の採用試験の2次募集実施――などのメニューを示しつつ、10月末までの計画提出を求めた。
文科省は各教委から寄せられた計画がすべて実現すれば、今回調査で796人だった「免許外」「臨時免許状」の各教員の合計人数は来年4月には80人に、24年度には0人になると見込む。11月には改めて計画実行を促す通知を出すほか、進み具合も点検する。情報だけを教える「専科教員」の配置や、一部の学校にとどまる見通しの情報Ⅱの授業実施校の拡大も促す方針だ。
各自治体には、地元の情報系大学や情報系専門学校、IT企業などとの産学官協議の場を創設して、情報の正規免許を持つ教員の養成や、専門知識を持つ社会人らの授業への派遣などを推進する仕組みも提示。国から支援金を出して後押しする考えだ。
また、今月からは文科省の特設サイトで情報Ⅰ、Ⅱの解説動画を順次配信し、生徒の学習の「直接支援」に乗り出す。
(桑原紀彦、編集委員・宮坂麻子)
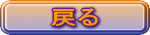
| copyright ⓒ2012 日本の「教育と福祉」を考える all rights reserved |
|