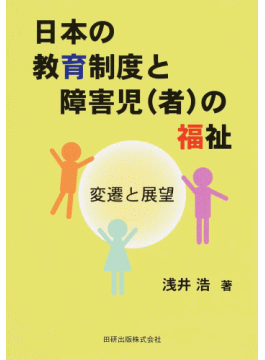日本の教育制度と障害児教育
《教育の義務化と学習指導要領と特別支援教育》
2025.8.20/2025.10.19/2025.11.24
2006年に、国連で障害に基づく差別の禁止を定めた「障害者権利条約」が採択されました。日本もこの条約に2007(平成19)年に外務大臣が署名し、2013(平成25)年12月に批准が正式に国会で承認され、翌年の1月に批准書を国連に寄託し、締約国となり、同年2月より日本においても障害者権利条約が発効しました。
障害者権利条約は、締約国に対して障害者差別をなくすことと、そのために必要な「合理的配慮」の提供を求めており、条約が守られているかどうかの審査を行うことになっています。
日本に対する国連の障害者権利委員会による初めての審査が2022(令和4)年8月にあり、翌月の9月9日に審査結果と勧告が公表されました。
勧告の内容には、障害のある児童生徒が通常学級から隔離されているとするインクルーシブ教育に関することが含まれており、当時の永岡桂子文部科学大臣はいち早く、9月13日の会見で、「現在、多様な学びの場において行われている特別支援教育を中止することは考えていない。勧告の趣旨を踏まえて、引き続きインクルーシブ教育システムの推進に努めたい。」との表明をしました。勧告の内容は尊重すべきで、真摯に受け止め、日本流の確かな対応をどう示すかはとても大切なことだと思います。
戦後、国民の基本的な権利の一つとして「教育を受ける権利」を定めた新たな日本国憲法が制定され、教育基本法と学校教育法により障害児の学校教育が義務制になった意義は大きと思います。しかし知的障害等の児童生徒のための養護学校(現在の特別支援学校)の義務制が施行されたのは、戦後の新教育法制度の発足から32年目の1974(昭和54)年4月1日からのことです。
多様化、多様性の時代などといわれていますが、教育の対象となる障害児童生徒も発達障害などその障害内容も多様化しています。さらに、障害児童だけでなく、不登校などの問題を抱える児童生徒の増加も顕在化しています。
戦後80年、日本の教育制度は、確かな理念に基づく抜本的な見直しが必要ではないかと考えます。
日本の学校教育制度と障害児教育
現在に至る日本の障害児教育の概略と課題
学習指導要領と教育課程について
学習指導要領とは何か?
日本の
学校教育制度と障害児教育
日本の学校教育は、戦前と戦後では大きく変化しています。その最初となるのが、明治新政府が1871(明治4)年に初めて全国の教育統括機関として文部省(現在の文部科学省)を設置し、翌1972(明治5)年に日本で最初の公教育のための法令である「学制」を発布したことにより始まりました。
学制とは、全国規模で学校を設置するための「学区制」のことで、大学校・中学校・小学校を基本に学校を体系化したものです。それら学校の設置単位となるのが学区で、その一番基礎となるのが小学校です。
明治新政府は、まず小学校の普及充実を目指し、「小学は教育の初級であるから人民一般必ず学ばなければならないものとする」と定め、文部省は小学校で教える「教科」の内容となる教科書の作成基準とその教授方法の概要を示す「小学教則」を作成しました。
教科とは、学校で教える主要な内容となる特定の学問分野を体系的にまとめたいわゆる国語、社会、算数、理科、などをいうわけで、それを教える指針となるのが小学教則です。それは現在の学習指導要領に相当するものと考えてよいと思います。
しかし学制の実施は、国民の教育的要求に対して支援をする制度というものではなく、国力増強を掲げ、学業を重視し、学力を優先する政策であったため、教科の内容は、従来の寺子屋※に見られたような「読・書・算(そろばん)」中心の内容とは異質で、国民の多くが実生活とはかけ離れたものとしてその必要性を認めず、就学拒否などの抵抗もあり、学制の実施に対する不満の高まりは、小学校の焼き打ちや打ちこわしといった事件なども引き起こしたという史実もあります。
こうして始まった小学校を基礎とする学校教育制度は、国民の抵抗はあったものの、学校へ行くことは立身出世に結びつくということになり、就学率も高まります。しかし当時の小学校には進級試験があり、学校の普及と就学率が高まるにつれ、教科中心の学業重視、学力優先の教育制度にはついていけないいわゆる「劣等生」「落第生」が出てくることになりました。それを放置できないとして、その対策を講ずる必要から能力別の学級編制である「落第生学級」と呼ばれる学級が編制されました。それが知的障害のための特殊学級であり、現在の特別支援学級の始まりです。
なお学制の規定には、小学は教育の初級であるから人民一般必ず学ばなければならないものとするという規定とともに、小学の種類として「廃人学校もなければならない」とあり、廃人とは心身の障害や病気のある人を意味します。したがって障害のある児童も教育の対象と考えられてはいたようですが、それは欧米の障害児の学校の存在を単に模しただけの規定であり、廃人学校が具体的にはどのような学校であったかは不明です。 「学制百二十年史」(文部省:平成4年発行)には、廃人学校は実際には存在しなかったということが記載されています。
いずれにしても明治新政府によって始まった教育制度は、教育を施す側の国力増強を目指す強い思いが込められた政策であり、教育を受ける側にとっては立身出世につながることになり、それは教科中心の学業を重視する学力優先の教育観となり、さらに学歴偏重となって日本国民のなかに根付くことになったと考えられます。そうした国民意識は、戦後日本の新たな教育法制度においても払拭されずにその根底に残されてきたといってよいと思います。このことはこれからの学校の在り方や義務教育、障害児教育などに関わる諸問題を考える上で踏まえておくべき重要な点だと思います。
※寺子屋
寺子屋とは、室町中期から明治初頭において武士や僧侶、神宮や医者その他の有識者が主に庶民の子どもを対象に開いた私塾の教育機関をいう。読み書き算(そろばん)を中心とする学習の場であった。学制の発足は、小学校の普及と充実に力点を置くもので、小学校新設については、その多くが庶民の代表的教育機関として存在していた寺子屋などの私塾を再編成する方式により、全国各地に急速に開設されていった。
現在に至る
日本の障害児教育の概略と課題
現在に至る日本の障害児教育は時代の変化とともに、国際的な動向とも関連しつつ進展してきましたが、大雑把に歴史をたどると、盲(視覚障害)と聾(ろう:聴覚障害)の場合は、1890(明治23)年には学校教育の対象とされ、1923(大正12)年には、「盲学校及び聾唖(ろうあ)学校令」により盲学校と聾唖学校(聾唖学校は聾学校の旧称))の設置が道府県に義務づけられています。しかし盲・聾以外の心身障害児のための学級や学校が設置されるようになるのは1941(昭和16)年に「国民学校令」が施行されてからであり、盲・聾以外の障害児の教育が義務教育として法制度上に明確に位置づけられたのは戦後のことです。
戦後の新しい日本国憲法に、国民の基本的な権利の一つとして「教育を受ける権利、受けさせる義務」が定められ、教育基本法と学校教育法が制定されたことによってはじめて、盲・聾以外の心身障害も含めた障害児の教育が義務教育として明確に教育法制度上に位置づけられ現在に至っています。
戦後の新しい教育制度は、小学校6年と中学校3年の9年間の学校教育を義務教育としました。そして障害児の教育も義務制にし、学校教育法は障害の有無で学校を分けて、障害種別に、盲学校、聾学校、養護学校(知的障害・肢体不自由・病弱が対象)に区分し、それらを「特殊教育諸学校」という括りで、そこでの教育を「特殊教育」と称してきました。その後、いわゆる「発達障害」の児童生徒への対応が問題となり、2006(平成18)年に、障害種別の学校区分をなくして、特別な教育的ニーズを抱える「発達障害」も含め、適切な教育指導と必要な支援を行うという目的で教育法制度の改正があり、2007(平成19)年4月から特殊教育諸学校は「特別支援学校」に一本化され、特殊教育は「特別支援教育」に改称されて現在に至っています。
障害児の教育が義務制になった意義は大きいと思います。しかし知的障害、肢体不自由、病弱(身体虚弱を含む)を対象とする養護学校(現在の特別支援学校)が設置されるようになるのは1956(昭和31)年に「公立養護学校整備特別措置法」(現在は廃止)が制定されてからのことであり、実際に養護学校の義務制が施行されたのは、戦後の新しい教育法制度の発足から32年目の1979(昭和54)年4月からのことです。
戦後の新しい教育法制度の発足から、養護学校の義務制の施行までになぜ30年以上もの年月を要したのかといえば、学校教育法の附則で、「この法律は昭和22年4月1日から、これを施行する。ただし、盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びにこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、勅令(昭和23年法律第133号により「政令」と改正)で、これを定める。」と規定されていたからです。
この附則により、昭和23年から学齢に達した盲(視覚障害)と聾(聴覚障害)の児童については、すでに大正時代にそのための盲学校と聾学校の設置が義務付けられていたことから、そのまま就学は義務となったのですが、知的障害等のための養護学校の義務制の実施については、そのための実績も乏しく、戦後の混乱と財政的窮乏等の中で、まず障害のない児童生徒のための小学校、中学校の義務教育を優先させたことから養護学校の義務化は遅れてしまったのです。
また、養護学校の義務化に向けた学習指導要領※の作成が大変難航したという経緯があります。それは知的障害等を対象とする教育も障害のない児童生徒対象の教科中心の教育内容や方法に「準ずる」ことが規定されていたからです。
養護学校の義務制の実施が遅れたことや、養護学校の学習指導要領の作成が難航したというのは、端的に言えば、日本の障害児教育の取り組みは、障害のない児童生徒の教育を優先する形で、「障害」についての社会的理解が十分とはいえない状況下で進展してきたことを意味します。
換言すれば、日本の教育制度は、国民の教育要求に寄り添い、支援する教育制度ではなく、国力増強を目的とする教科学習中心の学業重視、学力優先の教育制度であり、知的発達に障害のある児童生徒への理解や配慮を欠くもので、障害のない子どもを対象に考えられた教育制度の枠に当てはめるような形で進展してきたということです。
そのため養護学校の義務制の実施は、その当初から教育の内容や方法をめぐる問題、学校卒業後の生活や就労支援をめぐる問題、さらに親亡き後などの問題等をめぐって、同じような論議を繰り返し現在に至る結果を招いたといっても過言ではないようです。それは、「インクルーシブ教育」や「共生社会」をめぐる問題を考えることとも無関係なことではないと考えます。
戦後80年の今、教員の働き方改革の問題も含めて、教育とは何か、誰のため、何のための義務教育か、学習指導要領とは何かを改めて考えてみるべきときであり、教育法制度の抜本的見直しも必要だと思います。
※学習指導要領
学習指導要領は、昭和22年に「教科課程、教科内容及びその取扱い」の基準として、試案の形で作成された。その後、昭和26年の全面的な改訂で、「教科課程」の用語は「教育課程」の用語に変換され、昭和33年の改訂からは、学校教育法施行規則の一部改正により、学習指導要領は教育課程の基準として文部大臣が公示する形の法的根拠に基づくものとなった。それ以来ほぼ10年ごとに改訂を重ねて現在に至っている。
学習指導要領と教育課程について
学習指導要領とは、学校で教える各教科の目標や内容、年間の授業時数、学年ごとの到達目標の指針となるもので、それは全国の学校で行う教育の質を一定レベルに保つこことを目的に、文部科学省が定め、全国の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に共通のものとして適用されます。
この全国共通の基準として示された学習指導要領を基に、各学校がそれぞれの地域や学校の特色等に応じて具体的な教育計画を柔軟に作成することになっています。この教育計画の作成のことを「教育課程(カリキュラム)の編成」と言います。
学習指導要領は、社会の変化や地域性や児童生徒に応じた教育の課題に対応しつつ全国的な教育水準を維持することを目的に約10年ごとに見直され、改訂されて現在に至っていますが、それはあくまでも具体的な教育課程(カリキュラム)編成の基準として関わるものされています。しかし教科書や学校の時間割は学習指導要領に基づいて作られており、一般的には「教育課程」とは学習指導要領によって決められているものと解釈されているところに現状の問題があるといってよいと思います。
現在の学習指導要領や教育課程(カリキュラム)編成のルーツは、明治新政府によって始まった学校教育制度にあるといってよいと思います。明治新政府は教育政策として、何よりもまず学校設置の一番基礎となる小学校の普及充実を目指し、全国の教育統括機関として文部省(現在の文部科学省)を設置し、文部省は小学校で教える「教科」の指針となる「小学教則」を作成しました。
教科とは、学校で教える主要な内容となる特定の学問分野を体系的にまとめたいわゆる、国語、社会、算数、理科、などをいうわけです。したがって小学教則は、現在の学習指導要領に相当するものと考えてよいと思います。
しかし明治新政府による学校教育の制度は、国民の教育要求に対する支援のための教育制度というよりも、国力増強を掲げて学業を重視し、学力を優先する教育政策であったわけです。そのため教科の内容は、庶民の実生活とはかけ離れた内容であると受け取られ、国民の多くがその必要性を認めず、抵抗もあったのですが、学校へ行くということは立身出世につながるということから、就学率も高まります。ところが、学校の普及と就学率が高まるにつれて、教科中心の学業を重視する、学力優先の教育にはついていけないいわゆる「劣等生」「落第生」が出てくることになり、それを放置できないとしてそのための能力別の学級が編制されました。それが特殊学級であり、現在の特別支援学級、特別支援学校、特別支援教育の始まりです。こうした歴史を振り返ってみることは教育の本質を考える上できわめて大切なことだと思います。
戦後の新しい教育制度における学習指導要領は、1947(昭和22)年に、「教科課程、教科内容及びその取扱い」の基準として試案の形で作成されました。それ以来、改訂を重ねて現在に至るわけですが、当初の学習指導要領では、「教育課程」という用語ではなく、「教科課程」という用語が使われていたのですが、1951(昭和26)年の全面的改訂では、「教科課程」は「教育課程」に用語が変換されました。それは、「教育とは教科を教えること」というのが当初の考え方だったのが、「教育とは単に教科を教えることだけではない」という考え方への変化が、「教科課程」から「教育課程」への用語の変換となったのだと思います。
学習指導要領が必要なものだとしても、多様化、多様性の時代といわれる現状において、特に、障害児教育という観点からいえば、障害観も変化し、いわゆる「発達障害」が特別支援教育の対象となっています。発達障害と一口に言っても、その内容や程度や状態は広範で多様です。しかも発達障害とされる児童生徒は増加の傾向にあり、そのための多様な教育的支援を考えた場合、そのすべてに対応することを前提に学習指導要領を考えるとなると、それは今以上に細かく盛りだくさんとなり、膨大となるのではないかと思います。それは柔軟性を欠き、指導要領が要領を得ないものになりかねないのではいでしょうか。
文部科学省は、2030年代の社会の変化を見据えて中央教育審議会(中教審)に諮問し、学習指導要領の改訂に向けた議論が現在進んでいるということですが、「教科課程」から「教育課程」への用語の変換経緯などの検証も意味があるように思います。
教育とは何か、義務教育とは何か、教科も大事だとは思いますが、知識や技能を教えることが教育か、それは授業時数を増やしてたくさん教え込むのがよいのかどうか、こうしたきわめて初歩的な問題を踏まえた確かな教育理念が確立しなければ、「インクルーシブ教育」も「共生社会」も単に看板を掲げたままになるのではないかと思います。
《参考要点》
〇学習指導要領とは、全国どの地域でも一定の教育水準を維持することを目的に、文部科学省が法的根拠に基づいて定めるもので、各学校が教育課程を編成・実施する際の基準となるものです。学習指導要領には小学校、中学校、高校別に、それぞれの教科や活動の目標や内容が示されており、道徳教育や外国語活動も含まれます。
〇学習指導要領とは、教育課程の基準であり、各学校の校長が責任を持って地域や児童生徒の実態を踏まえた教育課程を編成するためのものです。それは画一的にすべての内容をそのまま実施するのではなく、地域の特色や児童生徒たちのニーズに応じて工夫が認められています。1958(昭和33)年の告示以降、おおむね10年ごとに改訂されてきましたが、学習指導要領と教育課程の関係については実際の教育現場においては認識のずれが生じているというのが現状のようです。
、
学習指導要領とは何か?
〈出典:文部科学省HP〉
全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学省では、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めています。これを「学習指導要領」といいます。
「学習指導要領」では、小学校、中学校、高等学校等ごとに、それぞれの教科等の目標や大まかな教育内容を定めています。また、これとは別に、学校教育法施行規則で、例えば小・中学校の教科等の年間の標準授業時数等が定められています。
各学校では、この「学習指導要領」や年間の標準授業時数等を踏まえ、地域や学校の実態に応じて、教育課程(カリキュラム)を編成しています。
学習指導要領が作成された背景と経緯
学習指導要領(試案)作成の目的を考える
学習指導要領の変遷
文部科学省:(資料)学習指導要領の改訂の経過
学習指導要領の意義と見直しの必要性
学習指導要領が
作成された背景と経緯
学習指導要領とは何かを考える上で、それが作成されることになった時代背景や経緯を理解することも大切だと思います。文部科学省:学制百年史編纂委員会「六 戦後の教育改革」(学制百年史 昭和56年9月5日発行)によれば、以下のようなことです。
〈背景〉
昭和二十年八月終戦によってわが国は連合国軍の占領下におかれることとなった。これより、二十七年平和条約の成立によって独立するに至るまでは、国政がすべて占領行政のもとにあって行なわれていた。この間に各分野にわたって改革の実施が要請されたが、教育改革はその中でも特に重要なものの一つとみられていた。これは教育を改革することによって、国民の思想や生活を改変し、これを新日本建設の土台とすることを基本方針としていたことによるのである。この間に急速に実施された教育改革は戦時下の教育の後をうけた特殊な方策によるものであって、常時の教育改革と同様にみることはできない。このようにして戦後の教育改革は占領政策の一部であったので、それらがすべてわが国独自の方策によるものではなかった。しかしこれらの教育改革の中には、それまでわが国における近代教育の発展を妨げていたものを、強力な方策によってとり除いて正常な発展の路線につかせ、さらに進展させたものも少なくなかった。
終戦直後二十年九月に、文部省は「新日本建設の教育方針」を示して、民主的・文化的国家建設のために必要と考えた教育の基本方針を明らかにしてこれを教育改革の出発点とした。その後同年十月より十二月にわたって連合国軍最高司令部(以下総司令部という。)は、日本教育制度の管理を始め四つの教育に関する指令をもって、戦時教育の処理についての方針を指示するとともに、速やかにこれを実施することを要請していた。文部省はこれらの占領政策による教育処理を実施して戦時教育体制を根本から改めるとともに、戦後の新教育建設について積極的な改革の諸方策を立てるために省内において協議を進め、具体的な改革の方針も立てようとしていた。二十一年にはその一つとして「新教育の指針」を編集し、戦後教育改革の基本となる思想を教育界に普及させることにも着手していた。総司令部は二十一年一月日本に向けて教育使節団を派遣することを本国へ要請した。使節団は三月に到着して教育改革の基本方策をまとめ報告書として総司令部に提出した。最高司令官はこの報告書に示された教育理念と改革の具体的な方策を承認し、これによって戦後日本の教育改革が進められることを要請した。総司令部の民間情報教育局(CIE)は報告書の趣旨を実現するため文部省と協議して具体的な方策を立てることとなった。これからCIEは政府および文部省の教育方策について助言し、協力し、その実施に当たっては背後において大きな力をもっていた。
|
〈経緯〉
以上のように学校や社会教育の制度は新しくなったが、これらの制度によって成立した教育機関においてどのような教育内容を授けるかはさらに重要な問題であった。昭和二十年秋から極端な国家主義や軍国主義を排除する目的で指令が発せられた。その中で教育内容についての戦後処置として注目されるのは二十年十二月の修身・地理・歴史の授業を停止し、戦時中使用されていた教科書をすべて回収すると指令したことである。この処置は新しい教育内容編成についての課題を与えたものである。ところが戦時教材処理の問題は国定教科書制度についての方針を再検討することとなり、新学制実施とともに、教科書は民間において編集し、文部省がこれを検定する制度に順次移行する方法がとられたのである。中等学校・師範学校の教科書は明治時代から検定制であったが、戦時中は国定制へ移行する政策がとられていた。教科書を国定制から検定制へ移行させることは、教育内容についての行政として大きな改革であった。教科書を検定したり、学習を指導したりするには教育内容の基準となるものが示されていなければならない。学校教育法においては、教育は学習指導要領によることと定められたのである。そこで学習指導要領は新学制による学校教育の出発に当たって必須なものとなった。特に新しい科目として登場した社会科や家庭科や自由研究などは、指導の基準となるものがなくては、授業を始めることができなかった。二十二年春に学習指導要領一般編を配布し、続いて各教科別の学習指導要領をつくった。しかしこの指導要領の作成はわが国においてはじめてのことであり、公表がせまられていたので、暫定のものとして急いで編集してまとめた。その際にアメリカ各州のコース・オブ・スタデイも参考にするところがあった。その後学習指導要領については実施状況を調査するとともに、この改正について研究し、二十四年に教育課程審議会を設置して、教育課程についての重要事項を審議して、教育内容編成の基本となる方針を立てることとなった。
|
 文部科学省:学制百年史編纂委員会「六 戦後の教育改革」(学制百年史 昭和56年9月5日)
文部科学省:学制百年史編纂委員会「六 戦後の教育改革」(学制百年史 昭和56年9月5日)
学習指導要領(試案)作成の
目的を考える
学習指導要領は、昭和22年3月に試案という形で初めて一般編が刊行され、同年内に算数科、家庭科、社会科、図画工作科、理科、音楽科及び国語科の各編が相次いで刊行され、昭和24年には体育科編が刊行されました。最初に作成された学習指導要領の序論には、試案として作成した意味等を含めて「一、なぜこの書はつくられたか 二、どんな研究の問題があるか 三、この書の内容」ということが記されています。
この序論は、学習指導要領とは何かを改めて考えるうえで示唆に富んでいると思います。
|
学習指導要領 一般編
(試案)
昭和二十二年度
文部省
序論
一、なぜこの書はつくられたか
(前文略)
これまでの教育では、その内容を中央できめると、それをどんなところでも、どんな児童にも一様にあてはめて行こうとした。だからどうしてもいわゆる画一的になって、教育の実際の場での創意や工夫がなされる余地がなかった。このようなことは、教育の実際にいろいろな不合理をもたらし、教育の生気をそぐようなことになった。たとえば、四月の初めには、どこでも桜の花のことを教えるようにきめられたために、あるところでは花はとっくに散ってしまったのに、それをおしえなくてはならないし、あるところではまだつぼみのかたい桜の木をながめながら花のことをおしえなくてはならない、といったようなことさえあった。また都会の児童も、山の中の児童も、そのまわりの状態のちがいなどにおかまいなく同じことをおしえられるといった不合理なこともあった。しかもそのようなやり方は、教育の現場で指導にあたる教師の立場を、機械的なものにしてしまって、自分の創意や工夫の力を失わせ、ために教育に生き生きした動きを少なくするようなことになり、時には教師の考えを、あてがわれたことを型どおりにおしえておけばよい、といった気持におとしいれ、ほんとうに生きた指導をしようとする心持を失わせるようなこともあったのである。
もちろん教育に一定の目標があることは事実である。また一つの骨組みに従って行くことを要求されていることも事実である。しかしそういう目標に達するためには、その骨組みに従いながらも、その地域の社会の特性や、学校の施設の実情やさらに児童の特性に応じて、それぞれの現場でそれらの事情にぴったりした内容を考え、その方法を工夫してこそよく行くのであって、ただあてがわれた型どおりにやるのでは、かえって目的を達するに遠くなるのである。またそういう工夫があってこそ、生きた教師の働きが求められるのであって、型のどおりにやるのなら教師は機械にすぎない。そのために熱意が失われがちになるのは当然といわなければならない。これからの教育が、本当に民主的な国民を育てあげて行こうとするならば、まずこのような点から改められなくてはなるまい。このために、直接に児童に接してその育成の任に当たる教師は、よくそれぞれの地域の社会の特性を見てとり、児童を知って、たえず教育の内容についても、方法についても工夫をこらして、これを適切なものにして、教育の目的を達するように努めなくてはなるまい。いまこの祖国の新しい出発に際して教育の負っている責任の重大であることは、いやしくも、教育者たるものの、だれもが痛感しているところである。われわれは児童を愛し、社会を愛し、国を愛し、そしてりっぱな国民を育てあげて、世界の文化の発展につくそうとする望みを胸において、あらんかぎりの努力をささげなくてはならない。そのためにまずわれわれの教壇生活をこのようして充実し、われわれの力で日本の教育をりっぱなものにしていくことがなによりたいせつなのではないだろうか。
この書は、学習の指導について述べるのが目的であるが、これまでの教師用書のように、一つの動かすことのできない道をきめて、それを示そうとするような目的でつくられたものではない。新しく児童の要求と社会の要求とに応じて生まれた教科課程をどんなふうにして生かしていくかを教師自身が自分で研究していく手びきとして書かれたものである。しかし、新しい学年のために短い時間で編集を進めなければならなかったため、すべてについて十分意を尽くすことができなかったし、教師各位の意見をまとめることもできなかった。ただこの編集のために作られた委員会の意見と、一部分の実際家の意見によって、とりいそぎまとめたものである。この書を読まれる人々は、これが全くの試みとして作られたことを念頭におかれ、今後完全なものをつくるために、続々と意見を寄せられて、その完成に協力されることを切に望むものである。
二、どんな研究の問題があるか
いま述べたように、教育をその現場の地域の社会に即し、児童に即して、適切なものにして行くためには、いったいどんなことを研究していったらよいであろうか。
まず第一に考えられることは、教育がその目標に達するように学習の指導をしようとすれば、わが国の一般社会、ならびにその学校のある地域の社会の特性を知り、その要求に耳を傾けなくてはならない。ここに一つの研究問題がある。
次に問題になるのは現実の児童の生活である。このことはだれでもすでに知っているように、児童は身ぢかな見なれたことを基にして新しいことを学びとって行くものである。また学習が十分な効果をあげるには、児童が積極的にみずからこれを学ぶのでなければならない。だから児童の生活からかけ離れた指導は、結局成果を得ることはできない。この意味において、教師が児童の指導をするにあたって、その素材を選ぶには、児童の興味や日常の活動を知ることが欠くことのできないところである。本書ではこの点を考えて、児童の活動や興味についての手がかりを得ることができるように、後に見るように、児童生活のあらましについてのべることにした。しかし、これはまだ決して完全なものではなく、一つの試みとしてのべたに過ぎないのであるし、そのうえ児童の生活は地域社会によって多かれ少なかれ違ったものを持っている。だから教師各位は、これにとらわれることなく。その地域の児童の生活の実情について、これをつかまえることに努力してもらいたい。そしてその的確なもの――すなわち児童の指導にあたって効果をあげるもの――については、これを大小となく報告をされた。これによってわれわれは近い将来において児童の発達に応じた活動を豊かにこの書におりこむことができるようになると思う。ここにまた一つの研究問題がある。
このようにして、教材についての研究が進められたとしても、学習指導の研究がそこに止まってはならないことはいうまでもない。すなわち次にはこれらをどうしたら児童がよく学んで行くことができるかを研究してみなくてはならない。たとえ教材が適切であっても指導の方法がよろしくなければ、とうていその効果をあげることはできない。そこで教師は学校の設備や教具について考え、その地域の児童の生活を知って、それらの上に方法を工夫しなければならない。これまでわが国の学校で行われていた指導法は、ともすると単純できまりきっていて、豊かな児童の生活の動きや、その地域の自然や社会の特性や、学校の設備などが生かされていないうらみがあった。われわれは、もっといきいきした豊かな方法を地域に即し、学校に即し、児童に即して研究しなくてはならない。ここにも研究の問題がある。この書は、このような工夫の参考にと思って指導方法の一般的なものについて述べたが、もとより完全なものではない。教師各位は現場の経験にもとづいていっそう適切な指導法を工夫することがたいせつである。
このようにして、教材の研究も方法の研究もきわめて必要であるが、それが単なる思いつきや主観的なものであってはならないことはもちろんである。その研究がいつも確実な基礎を持った科学的な考え方でなされなくてはならない。それには特に指導の結果を正確に調べて、そこから教材なり指導法なりを吟味することがたいせつである。つまり正確な指導結果の考査によって教材や指導法の適不適をしらべる材料を得て、これによって進めていくことが必要なのである。しかもこの考査によって、児童もまた、自分が学習の目的にどの程度近づいたかを知って、みずからの学習について反省の資料を得ることができるのである。ここでわれわれはどうしたら学習の結果を正確にしらべることができるかを研究する必要がある。この書はこの点についても一応その方法をのべたのであるが、教師各位はこれを参考にされて、もっと適切な方法を工夫して指導をいっそう効果あるようにする資料とされたい。
三、この書の内容
以上のような趣旨でこの書は上に述べたような研究への手引きとなるためにつくられたのである。
そこで次にまずその一般論として、今日のわが国の社会のありさまからみて、どんな教育の目標が考えられるべきかを述べ、新しい教科課程をかかげ、それとともに児童生活の発達と指導方法の一般ならびに指導結果の考査法とを、概説することとした。
各教科の指導要領ではそれぞれの教科の指導目標と、その教科を学習して行くために働く児童の能力の発達を述べ、教材のたての関係を見るための単元の一覧表をかかげ、その教科の指導法と指導結果の考査法とを概説することにした。そして各学年の指導内容については単元を分けて、その目標、指導方法、指導結果の考査法について参考となる事項をあげておいた。
これまでもしばしば述べたように、この書は不完全ではあっても、このようなことについての現場の研究の手引きとなることを志したのであって、その完成は今後全国の教師各位の協力にまたななくてはならない。そのために別に現場の経験や意見を報告していただく報告票を刊行することになっている。各位はこれによって本書の改訂に協力していただきたい。この幼い研究の手引きが、各位の協力によって将来健康に成長することを確信して、この書をお手もとにとどける。切に熱心な研究と協力とを望む次第である。
|
学習指導要領の変遷
「学習指導要領」は、戦後すぐに試案として作られたわけですが、現在のような大臣告示の形で定められたのは昭和33年のことであり、それ以来、ほぼ10年毎に改訂されてきました。
それぞれの改訂における、主なねらいと特徴は、以下のようなことです。
○ 昭和22年の学習指導要領
この最初の学習指導要領は試案として作成され、昭和22年3月に一般編が刊行され,同年内に算数科,家庭科,社会科,図画工作科,理科,音楽科及び国語科の各編が相次いで刊行され,昭和24年には体育科編が刊行された。
従来の修身(公民),日本歴史及び地理を廃止し,新たに社会科を設けたこと。
○ 昭和26年の改訂
全面的に改訂され,昭和22年の場合と同様に,一般編と各教科編に分けて試案の形で刊行された。
昭和22年の学習指導要領の「教科課程」という用語に代えて「教育課程」という用語が用いられた。
○ 昭和33~35年改訂
教育課程の基準としての性格の明確化(道徳の時間の新設、系統的な学習を重視、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等)
○ 昭和43~45年改訂
教育内容の一層の向上(「教育内容の現代化」) 時代の進展に対応した教育内容の導入(算数における集合の導入等)
○ 昭和52~53年改訂
ゆとりのある充実した学校生活の実現 =学習負担の適正化(各教科等の目標・内容を中核的事項にしぼる)
○ 平成元年改訂
社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成(生活科の新設、道徳教育の充実等)
○ 平成10~11年改訂
基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成(教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設等
学習指導要領の改訂の経過
 文部科学省:(資料)学習指導要領の改訂の経過
文部科学省:(資料)学習指導要領の改訂の経過
(資 料)
学習指導要領等の
改訂の経過
平成20年の小学校学習指導要領の改訂は、昭和22年に「教科課程,教科内容及びその取扱い」の基準として、初めて学習指導要領が編集、刊行されて以来、昭和26年、33年、43年、52年、平成元年、10年の全面改訂に続く7回目の全面改訂である。
昭和22年3月に学校教育法が制定されて,小学校教育は根本的な変革がなされ,教育課程についても大きな改革がなされた。すなわち,同年5月に学校教育法施行規則が制定され,学校教育法第20条の規定に基づいて教育課程(当時は「教科課程」と称していた。)に関する基本的な事項を定めるとともに,教育課程の基準としての学習指導要領を試案の形で作成した。
(1) 昭和22年の学習指導要領
この最初の学習指導要領については,昭和22年3月に一般編が刊行され,同年内に算数科,家庭科,社会科,図画工作科,理科,音楽科及び国語科の各編が相次いで刊行され,昭和24年には体育科編が刊行された。この最初の学習指導要領における特色は次のとおりである。
ア 従来の修身(公民),日本歴史及び地理を廃止し,新たに社会科を設けたこと。
社会科は,児童が自分たちの社会に正しく適応し,その中で望ましい人間関係を実現し,進んで自分たちの属する共同社会を進歩向上させることができるように,社会生活を理解させ,社会的態度や社会的能力を養うことを目標とした。
イ 新たに家庭科を設けたこと。
家庭科は,従来女子だけに課していた裁縫や家事と異なり,男女共に課し,望ましい家族関係の理解と家族の一員としての自覚の下に,家庭生活に必要な技術を修めて生活の向上を図る態度や能力を養うことを目標とした。
ウ 新たに自由研究を設けたこと。
自由研究は,児童の自発的な活動を促すために,教師の指導の下に児童がそれぞれの興味と能力に応じて,教科の発展として行う活動や学年の区別なく同好の者が集まって行うクラブ活動などを行う時間として設けた。
エ 各教科の授業時数を改めたこと。
授業時数については,指導に弾力性をもたせるという趣旨から,各教科とも年間の総時数で表し,1年間を35週とした場合の週当たりの授業時数を併せて示した。また,日課表を作成する上で1単位時間を特に固定せず,学習の進み方などの必要に応じて変化のある学習が行われるようにした。
(2) 昭和26年の改訂
昭和22年の学習指導要領は,戦後の教育改革の急に迫られて極めて短時日の間に作成されたもので,例えば,教科間の関連が十分図られていなかったことなどの問題があった。そこで,昭和23年以降学習指導要領の使用状況の調査を行う一方,実験学校における研究,編集委員会による問題点の研究などを行い,その改訂作業を
始めた。さらに,昭和24年には,小学校,中学校及び高等学校の教育課程に関する事項の調査審議を行うための教育課程審議会を文部省に設け,同審議会から,昭和25年6月には小学校家庭科の存否,毛筆習字の課程の取扱い,自由研究の存否,総授業時数の改正などについて,昭和26年1月には道徳教育の振興について答申を受けた。
このような経過を経て,学習指導要領は,昭和26年に全面的に改訂され,昭和22年の場合と同様に,一般編と各教科編に分けて試案の形で刊行された。その改訂の主な特色は次のとおりである。
ア 各教科の配当授業時数については,教科を学習の基礎となる教科(国語,算数),社会や自然についての問題解決を図る教科(社会,理科),主として創造的な表現活動を行う教科(音楽,図画工作,家庭),健康の保持増進を図る教科(体育)の4つの経験領域に分け,これらに充てる授業時数を教科の総授業時数に対する比率で示すこととし,教科と教科以外の総授業時数の基準を2個学年ごとにまとめて示したこと。
イ 家庭科(第5,第6学年)は他の教科と著しく重複する目標や指導内容を整理して存置することとしたこと。
ウ 毛筆習字は,国語学習の一部として第4学年から課すことができるようにしたこと。
エ 自由研究を発展的に解消し,教科の学習では達成されない目標に対する諸活動を包括して教科以外の活動とし,それらの活動を例示したこと。
また,道徳教育については,昭和26年の教育課程審議会の答申に基づいて,「道徳教育のための手引書要綱」を作成するとともに,学習指導要領一般編において,道徳教育は学校教育のあらゆる機会に指導すべきであるとし,社会科をはじめ各教科の道徳教育についての役割を明確にした。さらに,健康教育についても同様に一
般編において,教科,教科以外の活動を含めてあらゆる機会を通じて行われることが望ましいとした。
なお,この学習指導要領においては,昭和22年の学習指導要領の「教科課程」という用語に代えて「教育課程」という用語が用いられた。その後,昭和28年に教育課程審議会から社会科の改善に関する答申を受け,「社会科の改善についての方策」を発表するとともに,この方策に沿って学習指導要領社会科編の改訂を行い,昭和30年12月に刊行した。この改訂においては,社会科に
おける道徳教育の在り方を一層明確にするとともに,地理,歴史教育の系統性,指導内容の学年別配当を明らかにし,また,政治,経済,社会等については,小学校段階としての範囲を明確にするとともに世界的な視野に立った国民的自覚を促すことなどを強調した。
(3) 昭和33年の改訂
昭和26年の学習指導要領については,全教科を通じて,戦後の新教育の潮流となっていた経験主義や単元学習に偏り過ぎる傾向があり,各教科のもつ系統性を重視
すべきではないかという問題があった。また,授業時数の定め方に幅があり過ぎるということもあり,地域による学力差が目立ち,国民の基礎教育という観点から基礎学力の充実が叫ばれるようになった。そのほか,基礎学力の充実に関連し科学技術教育の振興が叫ばれ,理科,算数の改善が要請された。
このような点を改善するため,昭和31年に教育課程審議会に「小学校・中学校教育課程の改善について」諮問し,昭和33年3月に同審議会から答申を受け,学習指導要領を全面的に改訂し,昭和36年4月から実施した。
学習指導要領の改訂に先だち,昭和33年8月に学校教育法施行規則の一部を改正した。その改正の要点は次のとおりである。
ア 学習指導要領は,教育課程の基準として文部大臣が公示するものであると改め, 学校教育法,同法施行規則,告示という法体系を整備して教育課程の基準としての性格を一層明確にしたこと。
イ 小学校の教育課程は,各教科,道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するということを明示したこと。
ウ 小学校における各教科及び道徳の年間最低授業時数を明示したこと。
このように,従来は学習指導要領で規定していた事項を学校教育法施行規則において規定したのも,昭和33年の改訂の特色の一つである。
また,学習指導要領は,従来は一般編及び各教科編から成っていたが,この改訂において一つの告示にまとめ,教育課程の基準として必要な事項を規定するにとどめた。
昭和33年の改訂は,独立国家の国民としての正しい自覚をもち,個性豊かな文化の創造と民主的な国家及び社会の建設に努め,国際社会において真に信頼され,尊敬されるような日本人の育成を目指して行った。その改訂の特色は次のとおりである。
ア 道徳の時間を特設して,道徳教育を徹底して行うようにしたこと。
イ 基礎学力の充実を図るために,国語,算数の内容を再検討してその充実を図るとともに授業時数を増やしたこと。
ウ 科学技術教育の向上を図るために,算数,理科の充実を図ったこと。
エ 地理,歴史教育を充実改善したこと。
オ 情操の陶冶,身体の健康,安全の指導を充実したこと。
カ 小・中学校の教育の内容の一貫性を図ったこと。
キ 各教科の目標及び指導内容を精選し,基本的な事項の学習に重点を置いたこと。
ク 教育課程の最低基準を示し,義務教育の水準の維持を図ったこと。
(4) 昭和43年の改訂
昭和33年の改訂後,我が国の国民生活の向上,文化の発展,社会情勢の進展はめざましいものがあり,また,我が国の国際的地位の向上とともにその果たすべき役
割もますます大きくなりつつあった。そこで,教育内容の一層の向上を図り,時代 の要請に応えるとともに,さらに,実施の経験にかんがみ,児童の発達の段階や個性,能力に即し,学校の実情に適合するように改善を行う必要があった。
このため,昭和40年6月に教育課程審議会に「小学校,中学校の教育課程の改善について」諮問し,同審議会から昭和42年10月に答申を受け,昭和43年7月に学校教育法施行規則の一部を改正するとともに学習指導要領を全面的に改訂し,昭和46年4月から実施した。
学校教育法施行規則の主な改正点は,次のとおりである。
ア 小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科,道徳並びに特別活動によって編成するものとしたこと。
イ 小学校の各学年における各教科及び道徳の授業時数を,最低時数から標準時数に改めたこと。
ウ 小学校の教育課程に関し,その改善に資する研究を行うため特に必要があり,かつ,児童の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,小学校学習指導要領等によらないこと
ができることとしたこと。
また,この学習指導要領の改訂の方針は次のとおりである。
ア 小学校の教育は,教育基本法及び学校教育法の示すところに基づいて人間形成における基礎的な能力の伸長を図り,国民育成の基礎を養うものであるとしたこ
と。
イ 人間形成の上から調和と統一のある教育課程の実現を図ったこと。すなわち,基本的な知識や技能を習得させるとともに,健康や体力の増進を図り,正しい判断力や創造性,豊かな情操や強い意志の素地を養い,さらには,国家及び社会について正しい理解と愛情を育てるものとしたこと。
ウ 指導内容は,義務教育9年間を見通し,小学校段階として有効・適切な基本的な事項に精選したこと。この場合,特に時代の進展に応ずるようにしたこと。
(5) 昭和52年の改訂
昭和43年の改訂後,我が国の学校教育は急速な発展を遂げ,昭和48年度には高等学校への進学率が90パーセントを超えるに至り,このような状況にどのように対応
するかということが課題となっていた。また,学校教育が知識の伝達に偏る傾向があるとの指摘もあり,真の意味における知育を充実し,児童生徒の知・徳・体の調和のとれた発達をどのように図っていくかということが課題になっていた。
そこで,昭和48年11月に教育課程審議会に「小学校,中学校及び高等学校の教育課程の改善について」諮問を行い,昭和51年12月に答申を受けた。答申においては,教育課程の基準の改善は,自ら考え正しく判断できる児童生徒の育成ということを重視しながら,次のようなねらいの達成を目指して行う必要があるとした。
① 人間性豊かな児童生徒を育てること。
② ゆとりのあるしかも充実した学校生活が送れるようにすること。
③ 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視するとともに児童生徒の個性や能力に応じた教育が行われるようにすること。
この答申を受けて,昭和52年7月23日に学校教育法施行規則の一部を改正するとともに,小学校学習指導要領を全面的に改訂し,昭和55年4月から実施した。この改訂においては,自ら考え正しく判断できる力をもつ児童生徒の育成を重視
し,次のような方針により改善を行った。
① 道徳教育や体育を一層重視し,知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒の育成を図ることとしたこと。
豊かな人間性を育てる上で必要な資質や徳性を児童の発達の段階に応じて十分身に付けるようにするため,各教科等の目標の設定や指導内容の構成に当たって,これらの資質や徳性の涵養に特に配慮した。
② 各教科の基礎的・基本的事項を確実に身に付けられるように教育内容を精選 し,創造的な能力の育成を図ることとしたこと。
各教科の指導内容については,次の4つの観点に立って,各学年段階において確実に身に付けさせるべき基礎的・基本的な事項に精選した。
ア 小・中・高等学校の指導内容の関連と学習の適時性を考慮して,各学年段階間の指導内容の再配分や精選を行った。
イ 各学年にわたって取り扱うことになっていた指導内容は必要に応じて集約化を図った。
ウ 各教科の指導内容の領域区分を整理統合した。
エ 各教科の目標を中核的なものに絞り,それを達成するための指導事項を基礎的・基本的なものに精選した。
③ ゆとりのある充実した学校生活を実現するため,各教科の標準授業時数を削減し,地域や学校の実態に即して授業時数の運用に創意工夫を加えることができるようにしたこと。
ゆとりのあるしかも充実した学校生活を実現するため,各教科の指導内容を精選するとともに,学校教育法施行規則の一部を改正し,第4学年では週当たり2単位時間,第5,6学年では4単位時間の標準授業時数の削減が行われた。このことによって,学校の教育活動にゆとりがもてるようにするとともに,地域や学校の実態に応じ創意を生かした教育活動が展開できるようにした。
④ 学習指導要領に定める各教科等の目標,内容を中核的事項にとどめ,教師の自発的な創意工夫を加えた学習指導が十分展開できるようにしたこと。
各教科等の目標や指導内容について中核的な事項のみを示すにとどめ,また,内容の取扱いについて指導上の留意事項や指導方法に関する事項などを大幅に削除した。このような大綱化を図ることによって学校や教師の創意工夫の余地を拡大した。
(6) 平成元年の改訂
昭和52年の改訂後,科学技術の進歩と経済の発展は,物質的な豊かさを生むとともに,情報化,国際化,価値観の多様化,核家族化,高齢化など,社会の各方面に大きな変化をもたらすに至った。しかも,これらの変化は,今後ますます拡大し,加速化することが予想された。
このような社会の変化に対応する観点から教育内容の見直しを行うことが求められていた。そこで,昭和60年9月に教育課程審議会に「幼稚園,小学校,中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について」諮問を行い,昭和62年12月に答申を受けた。答申においては,次の諸点に留意して改善を図ることを提言している。
① 豊かな心をもち,たくましく生きる人間の育成を図ること。
② 自ら学ぶ意欲と社会の変化に主体的に対応できる能力の育成を重視すること。
③ 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視し,個性を生かす教育の充実を図ること。
④ 国際理解を深め,我が国の文化と伝統を尊重する態度の育成を重視すること。
この答申を受けて,平成元年3月15日に学校教育法施行規則の一部を改正するとともに,小学校学習指導要領を全面的に改訂し,平成4年4月から実施した。
学校教育法施行規則の主な改正点は,第1学年及び第2学年に,新教科として生活科を設定することとし,これに伴い,第1学年及び第2学年の社会及び理科は廃
止したことである。各教科等の授業時数については,各学年の年間の総授業時数は 変更しないが,第1学年及び第2学年に新設する生活科については,第1学年102
単位時間,第2学年105単位時間をそれぞれ充てるとともに,第1学年及び第2学年において,国語の力の充実を図るため,国語の授業時数を第1学年34単位時間,第2学年35単位時間それぞれ増やした。
この改訂においては,生涯学習の基盤を培うという観点に立ち,21世紀を目指し社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を図ることを基本的なねらいとし,次の方針により行った。
① 教育活動全体を通じて,児童の発達の段階や各教科等の特性に応じ,豊かな心をもち,たくましく生きる人間の育成を図ること。
これからの社会において自主的,自律的に生きる力を育てるため,道徳を中心にして各教科や特別活動においても,それぞれの特質に応じて,内容や指導方法の改善を図ることに配慮した。
② 国民として必要とされる基礎的・基本的な内容を重視し,個性を生かす教育を充実するとともに,幼稚園教育や中学校教育との関連を緊密にして各教科等の内
容の一貫性を図ること。
各教科の内容については,小学校段階において確実に身に付けさせるべき基礎 的・基本的な内容に一層の精選を図るとともに,基礎的・基本的な内容を児童一
人一人に確実に身に付けさせるようにするため,個に応じた指導など指導方法の改善を図ることとした。また,個性を生かすためには,児童一人一人が自分のも
のの見方や考え方をもつようにすることが大切であり,各教科において思考力,判断力,表現力等の能力の育成や,自ら学ぶ意欲や主体的な学習の仕方を身に付
けさせることを重視した。
③ 社会の変化に主体的に対応できる能力の育成や創造性の基礎を培うことを重視 するとともに,自ら学ぶ意欲を高めるようにすること。
各教科の内容については,これからの社会の変化に主体的に対応できるよう, 思考力,判断力,表現力等の能力の育成を重視することとした。また,生涯学習の基礎を培う観点から,学ぶことの楽しさや成就感を体得させ自ら学ぶ意欲を育てるため体験的な学習や問題解決的な学習を重視して各教科の内容の改善を行った。
④ 我が国の文化と伝統を尊重する態度の育成を重視するとともに,世界の文化や歴史についての理解を深め,国際社会に生きる日本人としての資質を養うこと。
我が国の文化と伝統に対する理解と関心を深め,それを大切にする態度の育成を図るとともに,日本人としての自覚やものの見方,考え方についての基礎を培う観点から,各教科等の内容の改善を図ることとした。その一環として,国旗及
び国歌の指導については,日本人としての自覚を高め国家社会への帰属意識を涵養するとともに,国際社会において信頼される日本人を育てる観点から,その充実を図ることとした。
(7) 平成10年の改訂
平成8年の中央教育審議会の「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」の第1次答申は,21世紀を展望し,我が国の教育について,[ゆとり]の中で[生きる力]をはぐくむことを重視することを提言した。[生きる力]について,同答申
は「いかに社会が変化しようと,自分で課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体 的に判断し,行動し,よりよく問題を解決する資質や能力」,「自らを律しつつ,他人とともに協調し,他人を思いやる心や感動する心など,豊かな人間性」,そして,「たくましく生きるための健康や体力」を重要な要素として挙げた。また,同答申は[ゆとり]の中で[生きる力]をはぐくむ観点から,完全学校週5日制の導入を提言するとともに,そのねらいを実現するためには,教育内容の厳選が是非とも必要であるとしている。
そこで,平成8年8月に教育課程審議会に「幼稚園,小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について」諮問を行い,平成10年7月に答申を受けた。答申においては,次の諸点に留意して改善を図ることを提言している。
① 豊かな人間性や社会性,国際社会に生きる日本人としての自覚の育成を重視すること。
② 多くの知識を一方的に教え込む教育を転換し,子どもたちの自ら学び自ら考える力の育成を重視すること。
③ ゆとりのある教育活動を展開する中で,基礎・基本の確実な定着を図り,個性を生かす教育の充実を図ること。
④ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育,特色ある学校づくりを進めること。
この答申を受けて,平成10年12月14日に学校教育法施行規則の一部を改正するとともに,小学校学習指導要領を全面的に改訂し,平成14年4月から実施した。
学校教育法施行規則の主な改正点は,第一に,各学校が,地域や学校,児童の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意
工夫を生かした教育活動を行う時間として,第3学年以上の各学年に「総合的な学習の時間」を創設したこと,第二に,各学年の年間総授業時数については,完全学校週5日制が実施されることに伴う土曜日分を縮減した時数とし,従前より各学年とも年間70単位時間(第1学年にあっては68単位時間),週当たりに換算して2単位時間削減することとし,また,各学年の各教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間ごとの授業時数についての改正を行ったこと,第三に,第3学年以上においても合科的な指導を進めることができるようにしたこと,の3点である。
この改訂においては,平成14年度から実施される完全学校週5日制の下で,各学校がゆとりの中で特色ある教育を展開し,児童に豊かな人間性や基礎・基本を身に付け,個性を生かし,自ら学び自ら考える力などの「生きる力」を培うことを基本的なねらいとして,次の方針により行った。
① 豊かな人間性や社会性,国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること。
児童の人間としての調和のとれた育成とともに国際社会の中で日本人としての自覚をもち主体的に生きていく上で必要な資質や能力の基礎を培う観点から,社会や体育,道徳,特別活動等において,それぞれの特質に応じて,内容や指導方法の改善を図ることに配慮した。
② 自ら学び,自ら考える力を育成すること。
これからの学校教育においては,多くの知識を教え込むことになりがちであった教育の基調を転換し,児童に自ら学び自ら考える力を育成することを重視した
教育を行うことが必要との観点から,総合的な学習の時間の創設のほか,各教科において体験的な学習や問題解決的な学習の充実を図った。
③ ゆとりのある教育活動を展開する中で,基礎・基本の確実な定着を図り,個性を生かす教育を充実すること。
完全学校週5日制を円滑に実施し,生涯学習の考え方を進めていくため,時間的にも精神的にもゆとりのある教育活動が展開される中で,児童が基礎・基本をじっくり学習できるようにするとともに,興味・関心に応じた学習に主体的に取
り組むことができるようにする必要がある。このような観点から,年間総授業時数の削減,各教科の教育内容を授業時数の縮減以上に厳選し基礎的・基本的な内
容に絞り,ゆとりの中でじっくり学習しその確実な定着を図るようにすることな どの改善を図った。また,児童が学習内容を確実に身に付けることができるよう
個別指導やグループ別指導,繰り返し指導,教師の協力的な指導など指導方法や指導体制を工夫改善し個に応じた指導を充実することを総則に示した。
④ 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育,特色ある学校づくりを進めること。
児童一人一人の個性を生かす教育を行うためには,各学校が児童や地域の実態 等を十分踏まえ,創意工夫を存分に生かした特色ある教育活動を展開することが大切である。このような観点から,総合的な学習の時間の創設や授業の1単位時間や授業時数の運用の弾力化,国語等の教科の目標や内容を2学年まとめるなどの大綱化といった改善を図った。
 文部科学省:特別支援学校学習指導要領等(平成29年4月公示・平成31年2月公示)
文部科学省:特別支援学校学習指導要領等(平成29年4月公示・平成31年2月公示)
 平成29年4月28日
平成29年4月28日
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに 特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する告示及び 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正
する告示の公示について(通知)
|
29文科初第236号
平成29年4月28日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各 都 道 府 県 知 事 殿
附属学校を置く各国立大学法人学長
構造改革特別区域法第12条第1項の
認定を受けた各地方公共団体の長
文部科学事務次官
戸 谷 一 夫
(印影印刷)
学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに 特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正する告示の公示について(通知)
このたび,平成29年文部科学省令第27号をもって,別添1のとおり学校教育法施行 規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)が制定され,また,平成29年文部科学省告示第72号及び第73号をもって,それぞれ別添2のとおり,特別支援学校幼稚部教育要領の全部を改正する告示(以下「新幼稚部教育要領」という。)及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の全部を改正する告示(以下「新小学部・中学部学習
指導要領」という。)が公示されました。
新幼稚部教育要領は平成30年4月1日から,改正省令及び新小学部・中学部学習指導要領は小学部については平成32年4月1日から,中学部については平成33年4月1日から施行されます。
今回の改正は,平成28年12月21日の中央教育審議会答申「幼稚園,小学校,中学 校,高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」(以下「答申」という。)を踏まえ,特別支援学校の幼稚部並びに特別支援学校の小学部及び中学部の教育課程の基準の改善を図ったものです。本改正の概要及び留意事項は下記のと
おりですので,十分に御了知いただき,改正省令,新幼稚部教育要領,新小学部・中学部 学習指導要領(以下「新学習指導要領等」という。)に基づく適切な教育課程の編成・実施及びこれらに伴い必要となる教育条件の整備を行うようお願いします。
また,都道府県教育委員会におかれては,所管の学校及び域内の市町村教育委員会その他の教育機関に対して,指定都市教育委員会におかれては,所管の学校その他の教育機関に対して,都道府県知事及び構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条
第1項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては,所轄の学校及び学校法人等に対して,附属学校を置く国立大学法人学長におかれては,その管下の学校に対して,本改正の
内容について周知を図るとともに,必要な指導等をお願いします。
なお,本通知については,関係資料と併せて文部科学省のホームページに掲載すること としておりますので,御参照ください。
記
1.改正の概要
(1)幼稚部,小学部及び中学部の教育課程の基準の改善の基本的な考え方
・ 教育基本法,学校教育法などを踏まえ,我が国のこれまでの教育実践の蓄積を活かし,豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される子供た
ちが急速に変化し予測不可能な未来社会において自立的に生き,社会の形成に参画するための資質・能力を一層確実に育成することとしたこと。その際,子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し,連携する「社会に開かれた教育課程」を重視したこと。
・ 知識及び技能の習得と思考力,判断力,表現力等の育成のバランスを重視する現行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で,知識の理解の質をさらに高め,
確かな学力を育成することとしたこと。
・ 先行する特別教科化など道徳教育の充実や体験活動の重視,体育・健康に関する指導の充実により,豊かな心や健やかな体を育成することとしたこと。また,自立活動の指導の充実により,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立して社会に参加する資質を養うこととしたこと。
・ 障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ,幼稚園,小・中・高等学 校の教育課程との連続性を重視したこと。
・ 障害の重度・重複化,多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実を図ったこと。
・ 新たに「前文」を設け,新学習指導要領等を定めるに当たっての考え方を,明確に示したこと。
(2)知識の理解の質を高め資質・能力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実現
○「何ができるようになるか」を明確化
・ 子供たちに育む「生きる力」を資質・能力として具体化し,「何のために学ぶのか」という学習の意義を共有しながら,授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を
引き出していけるよう,各教科等の目標及び内容を,①知識及び技能,②思考力, 判断力,表現力等,③学びに向かう力,人間性等の三つの柱で再整理したこと。
○主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
・ 我が国のこれまでの教育実践の蓄積に基づく授業改善の活性化により,児童生徒 の知識の理解の質の向上を図り,これからの時代に求められる資質・能力を育んで
いくことが重要であること。そのため,小学部及び中学部においては,これまでの教育実践の蓄積をしっかりと引き継ぎ,子供たちの実態や教科等の学習内容等に応じた指導の工夫改善を図ること。
・ 上記の資質・能力の三つの柱が,偏りなく実現されるよう,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら,子供たちの主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこととしたこと。
(3)各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立
・ 教科等の目標や内容を見渡し,特に学習の基盤となる資質・能力(言語能力,情報活用能力,問題発見・解決能力等)や豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次
代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには,教科等横断的な学習を充実する必要があること。
また,主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善については,1単位時間の授業の中で全てが実現できるものではなく,単元など内容や時間のまとまりの中で,習得・活用・探究のバランスを工夫することが重要であるとしたこと。その
際,障害の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度等を考慮して,個別の指導計画に基づき,基礎的・基本的な事項に重点を置くなど,指導方法や指導体制の工夫改善に努めることとしたこと。
・ そのため,学校全体として,子供たちや学校,地域の実態を適切に把握し,教育内容や時間の適切な配分,必要な人的・物的体制の確保,実施状況に基づく改善などを通して,教育課程に基づく教育活動の質を向上させ,学習の効果の最大化を図
るカリキュラム・マネジメントに努めるものとしたこと。特に,個別の指導計画の実施状況の評価と改善を,教育課程の評価と改善につなげていくよう努めるものと
したこと。
(4)幼稚部における主な改善事項
・ 幼稚部教育要領においては,幼稚部における教育において育みたい資質・能力 (「知識及び技能の基礎」,「思考力,判断力,表現力等の基礎」,「学びに向かう力,人間性等」)を明確にしたこと。
・ 5歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿を「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として明確にしたこと。(「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・
規範意識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関わり・ 生命尊重」「数量や図形,標識や文字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」
「豊かな感性と表現」)
・ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」は,幼児の障害の状態や特性及び発達の程度等に応じて,指導を行う際に考慮するものとしたこと。
(5)小学部・中学部における主な改善事項
① 小・中学校の教育内容の改善に準じた主な改善事項 小学校学習指導要領(平成29年3月31日文部科学省告示第63号)及び中学校教育要領(平成29年3月31日文部科学省告示第64号)の改善に準じた改善を行ったこと。
ア 言語能力の確実な育成
・ 発達の段階に応じた,語彙の確実な習得,意見と根拠,具体と抽象を押さえて考えるなど情報を正確に理解し適切に表現する力の育成を図ることとしたこと。
・ 学習の基盤としての各教科等における言語活動(実験レポートの作成,立場や根拠を明確にして議論することなど)を充実させたこと。
イ 情報活用能力の育成
・ コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な 環境を整え,これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることとしたこと。
・ 小学部においては,各教科等の特質に応じて,コンピュータでの文字入力等の習得,プログラミング的思考の育成のための学習活動を実施することとしたこと。
ウ 理数教育の充実
・ 前回改訂において充実させた内容を今回も維持した上で,日常生活等から問題を見いだす活動や見通しをもった観察・実験などを充実させたこと。
・ 必要なデータを収集・分析し,その傾向を踏まえて課題を解決するための統計教育や自然災害に関する内容を充実させたこと。
エ 伝統や文化に関する教育の充実
・ 古典など我が国の言語文化や,県内の主な文化財や年中行事の理解,我が国や郷土の音楽,和楽器,武道,和食や和服などの指導を充実させたこと。
オ 体験活動の充実
・ 生命の有限性や自然の大切さ,挑戦や他者との協働の重要性を実感するため, 体験活動を充実させ,自然の中での集団宿泊体験活動や職場体験を重視したこと。
カ 外国語教育の充実
・ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者及び病弱者(以下「視覚障害者等」と いう。)である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,中学年
で「外国語活動」を,高学年で「外国語科」を導入したこと。(なお,外国語教育の充実に当たっては,新教材の整備,研修,外部人材の活用などの条件整備を行い支援することとしている。)
・ 小・中・高等部一貫した学びを重視し,外国語能力の向上を図る目標を設定するとともに,国語教育との連携を図り日本語の特徴や言語の豊かさに気付く指導を充実させたこと。
② 道徳教育の充実
・ 平成27年3月27日付け26文科初1339号「学校教育法施行規則の一部 を改正する省令の制定,小学校学習指導要領の一部を改正する告示,中学校学習
指導要領の一部を改正する告示及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領の一部を改正する告示の公示並びに移行措置等について(通知)」により既にお伝えしたとおりであり,小学部で平成30年4月1日から,中学部で平成31年4
月1日から施行される内容に変更はないこと。なお,知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において,内容の指導に当たっての配慮事項の一部を加えたこと。
平成27年の一部改正の内容は,道徳の時間を教育課程上,特別の教科である道徳(以下「道徳科」という。)として新たに位置付け,発達の段階に応じ,答えが一つではない課題を一人一人の児童生徒が道徳的な問題と捉え向き合う「考える道徳」,「議論する道徳」へと転換を図るものであること。
・道徳科の内容項目について,いじめ問題への対応の充実や発達の段階をより一 層踏まえた体系的なものに見直すとともに,問題解決的な学習や体験的な学習な
どを取り入れ,指導方法の工夫を行うことについて示したこと。
・ 道徳科における学習状況及び道徳性に係る成長の様子を継続的に把握し,指導の改善に生かすこと。ただし,数値による評価は行わないこと。
具体的には,平成28年7月29日付け28文科初第604号「学習指導要領の一部改正に伴う小学校,中学校及び特別支援学校小学部・中学部における児童
生徒の学習評価及び指導要録の改善等について(通知)」(以下「道徳科の学習評 価及び指導要録の改善通知」という。)においてお知らせしたとおり,他の児童
生徒との比較ではなく,児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止めて認め, 励ます個人内評価として記述により行うこと。
③ 学びの連続性を重視した対応
ア 「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」について,児童生徒の学びの連続性 を確保する視点から,基本的な考え方を規定したこと。
イ 知的障害者である児童生徒のための各教科等の目標や内容について,育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づき整理するとともに,各部や各段階,幼稚園や小・
中学校とのつながりに留意し,次の点を充実したこと。
・ 中学部に二つの段階を新設するとともに,小・中学部の各段階に目標を設定し, 段階ごとの内容を充実したこと。
・ 小学部の教育課程に外国語活動を設けることができることを規定したこと。
・ 知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ,小学部に就学する児童のうち,小学部の3段階に示す各教科又は外国語活動の内容を習得し目標を達成している者又は中学部に就学する生徒のうち,中学部の2段階に示す各教科の内容を習得し目標を達成している者については,相当する学校段階までの小
学校等の学習指導要領の各教科及び外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができるよう規定したこと。
④ 一人一人に応じた指導の充実
・ 視覚障害者等である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校において,児童生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮し,育成を目指す資質・能力を育むため,障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実したこと。
【視覚障害】 空間や時間の概念形成の充実
【聴覚障害】 音声,文字,手話,指文字等を活用した意思の相互伝達の充実
【肢体不自由】 体験的な活動を通した的確な言語概念等の形成
【病弱】 間接体験,疑似体験等を取り入れた指導方法の工夫
・ 発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため,自立活動の内容として,「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定したこと。
⑤ 自立と社会参加に向けた教育の充実
・ 卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行 うことを規定したこと。
・ 小学部,中学部段階からのキャリア教育の充実を図ることを規定したこと。また,幼稚部においても,「自立心」,「協同性」,「社会生活との関わり」といった
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を示したこと。
・ 生涯学習への意欲を高めることや,生涯を通じてスポーツや芸術文化活動に親しみ,豊かな生活を営むことができるよう配慮することを規定したこと。
・ 障害のない子供との交流及び共同学習の機会を設け,共に尊重し合いながら協 働して生活していく態度を育むことを明らかにしたこと。
・ 日常生活に必要な国語の特徴や使い方〔国語〕,数学を学習や生活で生かすこと 〔算数,数学〕,身近な生活に関する制度〔社会〕,働くことの意義,消費生活と環
境〔職業・家庭〕など,知的障害者である児童生徒のための各教科の内容を充実し たこと。
⑥ その他の改善事項
・ 初等中等教育の一貫した学びを充実させるため,小学部入学当初における生活科を中心とした「スタートカリキュラム」を充実させるとともに,幼小,小中,中高といった学部段階間及び学校段階間の円滑な接続や教科等横断的な学習を重
視したこと。
・ 児童生徒一人一人の調和的な発達を支える観点から,学級経営や生徒指導,キ ャリア教育の充実と教育課程の関係について,小学部及び中学部を通して明記し
たこと。
・ 日本語の習得に困難のある児童生徒への教育課程,夜間その他の特別の時間に授業を行う課程について定めたこと。
・ 部活動については,教育課程外の学校教育活動として教育課程との関連を留意 し,社会教育関係団体等との連携による持続可能な運営体制について定めたこと。
2.留意事項
(1)移行措置期間の特例
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間における現行の小学部・中学 部学習指導要領(平成21年文部科学省告示第62号)の必要な特例については,追ってこれを告示し,別途通知する予定であること。
(2)特別支援学校教諭等免許状の早期取得促進
平成27年12月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力 の向上について」において,平成32年までにおおむね全ての特別支援学校教員が当該
学校教諭等免許状を保有することを目指すとされたことを踏まえ,特別支援学校教諭等免許状保有者の特別支援学校への採用・配置,同免許状を保有しない特別支援学校教員に対する免許法認定講習の受講促進など,計画的な同免許状保有率向上の取組を進め,
特別支援学校教員の専門性向上に引き続き努めること。
(3)新学習指導要領等の実施に必要な諸条件の整備
答申において指摘されているとおり,新学習指導要領等の実現のためには,これからの学校教育の在り方に関わる諸改革との連携を図るとともに,教員の授業改善や子供と向き合う時間を確保するなど,教員一人一人が力を発揮できるような教育条件の整備に努める必要があること。
具体的には,平成29年4月から施行された教育公務員特例法等の改正を受け,教員養成・採用・研修を一体として,教員の資質・能力の向上を図ること。子供一人一人の学びを充実させるためのきめ細かな指導など新学習指導要領等における指導や業務の在り方に対応する指導体制の充実を図ること。教職員の業務の見直しや部活動の運営の適正化などによる業務の適正化を図ること。学校図書館の充実やICT環境の整備など教材や教育環境の整備・充実を図ること。
特に,特別支援学校において教室不足が生じている状況を踏まえ,各設置者において,その解消計画を策定・更新するとともに,新設校の設置,校舎の増築,分校・分教室による対応,廃校・余裕教室等の既存施設の活用等により,引き続き教室不足解消のため
の取組を進めること。
(4)新学習指導要領等の周知・徹底
新学習指導要領等の理念が各学校において実現するためには,各学校の教職員が新学習指導要領等の理念や内容についての理解を深める必要がある。このため,文部科学省
としては平成29年度に新学習指導要領等に関する説明会を開催するとともに,一人一 人の教職員が直接利用できる各種の広報媒体を通じて,周知・徹底を図ることとしており,各教育委員会等においても,新学習指導要領等に関する研修会を開催,教職員への周知・徹底を図ること。
また,学習指導要領は大綱的な基準であることから,その記述の意味や解釈などの詳細については,文部科学省が作成・公表する学習指導要領解説において説明することを予定している。このため,学習指導要領解説を活用して,教職員が学習指導要領についての理解を深められるよう周知・徹底を図ること。
(5)家庭・地域等との連携・協働の推進
学校がその目的を達成するため,各教育委員会等においては,学校や地域の実態等に応じ,教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど,家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また,高齢者や異年齢の子供など,地域における世代を越えた交流の機会を設けること。
〔参考〕文部科学省ホームページアドレス
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
本件担当: 文部科学省 電話:03(5253)4111(代表)
初等中等教育局 特別支援教育課(内線2003
|
特別支援学校学習指導要領等の
改訂のポイント
( 文部科学省:特別支援学校学習指導要領等の改訂のポイント 文部科学省:特別支援学校学習指導要領等の改訂のポイント
1.今回の改訂の基本的な考え方
【幼稚部教育要領、小学部・中学部学習指導要領】
● 社会に開かれた教育課程の実現、育成を目指す資質・能力、主体的・対話的で深い学びの視点を踏まえた指導改善、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立など、初等中等教育全体の改善・充実の方向性を重視。
● 障害のある子供たちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ、幼稚園、小・中・高等学校の教育課程との連続性を重視。
● 障害の重度・重複化、多様化への対応と卒業後の自立と社会参加に向けた充実。
2.教育内容等の主な改善事項
学びの連続性を重視した対応
● 「重複障害者等に関する教育課程の取扱い※」について、子供たちの学びの連続性を確保する視点から、基本的な考え方を規定。
※当該学年の各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができることや、各教科及び 道徳科の目標及び内容に関する事項を前各学年の目標及び内容に替えたりすることができるなどの規定。
● 知的障害者である子供のための各教科等の目標や内容について、育成を目指す資質・能力の 三つの柱に基づき整理。その際、各部や各段階、幼稚園や小・中学校とのつながりに留意し、次の点を充実。
・中学部に二つの段階を新設、小・中学部の各段階に目標を設定、段階ごとの内容を充実
・小学部の教育課程に外国語活動を設けることができることを規定
・知的障害の程度や学習状況等の個人差が大きいことを踏まえ、特に必要がある場合には、個別の指導計画に基づき、相当する学校段階までの小学校等の学習指導要領の各教科の目標及び内容を参考に指導ができるよう規定
一人一人に応じた指導の充実
● 視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者及び病弱者である子供に対する教育を行う特別支援学校において、子供の障害の状態や特性等を十分考慮し、育成を目指す資質・能力を育むため、
障害の特性等に応じた指導上の配慮を充実するとともに、コンピュータ等の情報機器(ICT機器)の活用等について規定。
【視覚障害】 空間や時間の概念形成の充実
【聴覚障害】 音声、文字、手話、指文字等を活用した意思の相互伝達の充実
【肢体不自由】体験的な活動を通した的確な言語概念等の形成
【病弱】 間接体験、疑似体験等を取り入れた指導方法の工夫
● 発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため、自立活動の内容として、「障害の特性の理解と生活環境の調整に関すること」などを規定。
自立と社会参加に向けた教育の充実
● 卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行うことを規定。
● 幼稚部、小学部、中学部段階からのキャリア教育の充実を図ることを規定。
●生涯学習への意欲を高めることや、生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ、豊かな生活を営むことができるよう配慮することを規定。
● 障害のない子供との交流及び共同学習を充実(心のバリアフリーのための交流及び共同学習)
● 日常生活に必要な国語の特徴や使い方〔国語〕、数学を学習や生活で生かすこと〔算数、数学〕、身近な生活に関する制度〔社会〕、働くことの意義、消費生活と環境〔職業・家庭〕など、知的障害者である子供のための各教科の内容を充実
 文部科学省:特別支援学校学習指導要領等(平成29年4月公示・平成31年2月公示) 文部科学省:特別支援学校学習指導要領等(平成29年4月公示・平成31年2月公示)
 文部科科学省:特別支援学校学習指導要領等の改訂のポイント 文部科科学省:特別支援学校学習指導要領等の改訂のポイント
 文部科学省:平成29・30・31年改訂学習指導要領(本文、解説) 文部科学省:平成29・30・31年改訂学習指導要領(本文、解説)
 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 総則編
(幼稚部・小学部・中学部) 平成30年3月
 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 自立活動編
(幼稚部・小学部・中学部) 平成30年3月
 特別支援学校小学部・中学部 学習評価参考資料 令和2年4月 文部科学省 特別支援学校小学部・中学部 学習評価参考資料 令和2年4月 文部科学省
 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に関する移行措置並びに 移行期間中における学習指導等について(通知) 特別支援学校小学部・中学部学習指導要領に関する移行措置並びに 移行期間中における学習指導等について(通知)
|
学習指導要領の
意義と見直しの必要性
戦後、障害児の教育も義務制になった意義は大きいと思います。しかし現在に至る学習指導要領の改訂過程は、教科学習中心の学力を重視するものであり、障害児の教育は、障害のない児童生徒のための教育法制度の枠に当てはめるような形で修正(改訂)を繰り返して進展してきたといってよいのではないでしょうか。それは建前論的にはよいのかもしれませんが、そこに問題や課題があるという点を直視して考えてみなければならないと思います。そうでなければ同じ繰り返しを続けることになると思います。
学習指導要領が必要なものだとしても、果たして規制力のあるものとして、細かな盛りだくさんの内容は必要なものなのかどうか、特に、障害児教育の義務制ということとの関連で考えた場合、抜本的に見直す必要があるように思います。
学習指導要領は、昭和22年に「教科課程、教科内容及びその取扱い」の基準として、試案の形で作成されて以来、改訂を重ね現在に至っているわけですが、試案として作成された学習指導要領(一般編 (試案) 昭和二十二年度 文部省)の序論「一、なぜこの書はつくられたか」には、重要視すべき以下のような内容が記されています。
学習指導要領 一般編 (試案) 昭和二十二年度 文部省 序論
「これまでの教育では、その内容を中央できめると、それをどんなところでも、どんな児童にも一様にあてはめて行こうとした。だからどうしてもいわゆる画一的になって、教育の実際の場での相違や工夫がなされる余地がなかった。このようなことは、教育の実際にいろいろな不合理をもたらし、教育の生気をそぐようなことになった。」
「もちろん教育に一定の目標があることは事実である。また一つの骨組みに従って行くことを要求されていることも事実である。しかしそういう目標に達するためには、その骨組みに従いながらも、その地域の社会の特性や、学校の施設の実情やさらに児童の特性に応じて、それぞれの現場でそれらの事情にぴったりした内容を考え、その方法を工夫してこそよく行くのであって、ただあてがわれた型どおりにやるのでは、かえって目的を達するに遠くなるのである。またそういう工夫があってこそ、生きた教師の働きが求められるのであって、型どおりにやるのなら教師は機械にすぎない。そのために熱意が失われがちになるのは当然といわなければならない。
この書は,学習の指導について述べるのが目的であるが、これまでの教師用書のように、一つの動かすことのできない道をきめて、それを示そうとするような目的でつくられたものではない。新しく児童の要求と社会の要求とに応じて生まれた教科課程をどんなふうにして生かして行くかを教師自身が自分で研究して行く手びきとして書かれたものである。しかし、新しい学年のために短い時間で編集を進めなければならなかったため、すべてについて十分意を尽くすことができなかったし、教師各位の意見をまとめることもできなかった。ただこの編集のために作られた委員会の意見と、—部分の実際家の意見によって、とりいそぎまとめたものである。この書を読まれる人々は、これが全くの試みとして作られたことを念頭におかれ、今後完全なものをつくるために、続々と意見を寄せられて、その完成に協力されることを切に望むものである。
|
インクルーシブ教育とは、すべての子どもが地域社会の学校教育の場に包み込まれ、それぞれに必要な教育が受けられるようにすることを意味するわけですが、教育を受ける権利で大切なことは、どのような教育をどのような方法で、どのような教育的環境条件の下で受けることができるかどうかということであるはずです。
「一人ひとりを大切にした教育」ということがいわれていますが、そこで重要なことは、一人ひとりに対して具体的にどのように対応していくかということです。障害のある人もない人も共にということは、単に画一的、一律的であることとはちがうはずです。
人としてよく育ち、よく生きるための教育であるならば、障害をもつ子どもの教育も、障害のない子どもの教育も、その教育目標は同じであるといってよいと思います。しかし障害児(者)にとって効果的な教育内容や方法を具体的に考えるということでは、その障害の内容や程度や状態に配慮する必要があります。
障害児教育の義務制の現状は、いわゆる発達障害の児童・生徒が増加傾向にあり、その障害の内容も状態も程度も多様化していると思います。
障害児者の教育を受ける権利を保障するからには、障害の内容やその程度や状態などの実情に配慮した多様な教育の場や機会が当たり前に用意されるということでなければなりませんし、そのための教育内容や教育方法等の創意、工夫ができるような教育制度でなければなりません。それが教育を受ける権利に対する教育を受けさせる義務ということだと思います。
したがって多様な教育内容や教育方法、教育の場や機会があり、そうした多様な教育内容や教育方法、教育の場や機会が当たり前に用意されるということが通常であるいう考えに基づく教育法制度でなければ、教育を受ける権利や学ぶ権利の保障にはならないと思います。
多様化・多様性の時代といわれる現状において、教育とは何かと考えたとき、日本の義務教育の制度における学習指導要領のあり方は、それに沿うものといえるのかどうか、あるいは教育を施す側の思い込みが、教育本来の〝足かせ〟になっているようなことはないのかどうかという観点に立ち、もっと実際の教育の現場に裁量を委ね、それを支援するという方向で見直す必要があるように思います。
教育とは、単に知識や技能的なものを教えればよいというだけではなく、人間社会の中でどのようによりよく生きて行くかを目指すところに大切な意味があるはずです。義務教育とはそのためのものでなければならないと思います。そうした確かな理念に基づく教育制度改革が「共生社会」「インクルーシブ教育」に通ずるものと思います。
現在に至る学習指導要領の改訂過程は、障害のない児童生徒のための教育法制度の枠に障害児教育を無理にあてはめるような形で修正(改訂)を繰り返して進展してきたといってもよいと思います。戦後80年、すべての児童生徒が義務教育の対象となっているわけですから、やはりその実態に即した教育法制度の抜本的見直しは必要だと思います。
 障害児教育の義務制の意義と課題
障害児教育の義務制の意義と課題
 日本の教育制度と特別支援教育について《提言》
日本の教育制度と特別支援教育について《提言》

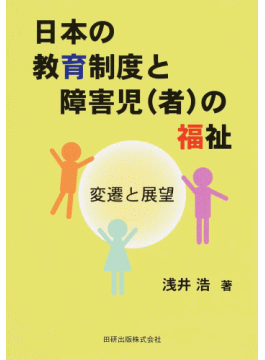
日本の障害児(者)の教育や福祉をめぐる問題、課題を考察し、今後を展望
田研出版 3190円 A5判 316頁
第1章 日本の障害児教育の始まりと福祉
義務教育の制度と障害児/学校教育と福祉施設/精神薄弱者福祉法(現:知的障害者福祉法)の制定/教育を受ける権利の保障
第2章 戦後の復興から社会福祉基礎構造改革へ
社会福祉法人制度と措置委託制度/社会の変化と社会福祉基礎構造改革/「措置」から「契約」への制度転換と問題点
/社会福祉法人制度改革の意義と課題
第3章 障害者自立支援法から障害者総合支援法へ
障害者自立支援法のねらい/障害者自立支援法をめぐる問題/自立支援法から総合支援法へ/障害者総合支援法施行3年後の見直し
第4章 教育の意義と福祉の意義
人間的成長発達の特質と教育・福祉/人間的進化と発達の個人差/教育と福祉の関係/「福祉」の意味と人権
第5章 展望所感
障害(者)観と用語の問題/新たな障害(者)観と国際生活機能分類の意義/障害児教育の義務制の意義と課題/障害者支援をめぐる問題
Ⓒ 2024 知的障害児者の教育と福祉