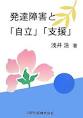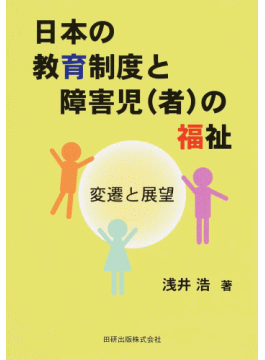発達障害者支援法の制定について
障害者施策において、身体的な障害もなく、知的障害でもないが、人間関係や社会生活への参加、就労などの面で明らかに困難を抱えているような場合については、それを「軽度発達障害」などとして、知的障害でもなく、身体障害でもなく、精神障害の範ちゅうでもないとして放置してきたという経緯があります。
つまり軽度というような場合は、これまでの身体障害・知的障害・精神障害の三障害を基本とする法律や制度に基づいた障害者施策の対象としては認定されにくく、その位置付けは不明確で法制度の谷間にあったことから、それらを「発達障害」として法的に明確にするために「発達障害者支援法」が制定されました。
発達障害者支援法は、2004(平成16)年12月に成立、公布。2005(平成17)年4月1日から施行されました。
注)平成28年5月25日:改正発達障害者支援法が成立
議員立法で平成17年に施行された発達障害者支援法の改正法が平成28年5月25日の参院本会議で可決、成立。
 厚生労働省:発達障害者支援法の改正について(PDF) 厚生労働省:発達障害者支援法の改正について(PDF)
発達障害についての定義
発達障害者支援法の第2条では、発達障害(者)について次のように定義しています。
発達障害者支援法(最新改正:平成28年)
(定義)
第2条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多
動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものを
いう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活
に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。
3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社
会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
4 この法律において、「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を
促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。
※「広汎性発達障害」というのは、自閉症及び自閉症に類似のアスペルガー症候群などの行動の障害を特徴とする広義の自閉的な発達障害群を意味する用語であり、必ずしも知的障害を有するものでないが、コミュニケーションや対人関係などで問題を抱える自閉性障害を含めた障害グループの総称です。その障害の内容や状態は多様で、広汎(広範)に及ぶことから広汎性発達障害といいます。
発達障害の内容や範囲について
発達障害は、脳機能の障害がその基盤にありますが、要するに何らかの原因により、人としての生活機能や生活能力の健やかな発達が阻害され、そのために日常生活・社会生活において何らかの支援を必要とするような問題を抱えています。
「発達障害」とは、発達期(人の成長発達の盛んな時期のことで、概ね18歳まで)において認知、言語、運動、社会性などにかかわる生活機能や生活能力の獲得に困難を抱える障害の総称だと理解すればよいと思います。。
肝心なことはその抱える問題を早期に発見し、それをどのように受け止め、どう支援するかです。
 文部科学省:「発達障害」の用語の使用について 文部科学省:「発達障害」の用語の使用について
発達障害の用語の使用について、文部科学省は、「学術的な発達障害と行政政策上の発達障害とは一致しない。また、調査の対象など正確さが求められる場合には、必要に応じて障害種を列記することなどを妨げるものではない。」(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課 平成19年3月15日)としています。
|
 発達障害をどのように理解するか 発達障害をどのように理解するか
発達障害者支援法は、知的障害(精神遅滞)を、法の直接の対象にはしていません。それは知的障害者福祉法等の他の法律により、すでに法的な対応措置を講じてきたからですが、ここでは知的障害(精神遅滞)も含めて、発達障害の内容についての概略を以下のようにまとめておきます。

《精神遅滞(知的障害)》 《自閉症 アスペルガー症候群》
《広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)》
精神遅滞(知的障害)
次の3条件が目安となる。
①知的機能(知能)の発達に明らかな遅れがある。
②適応行動の障害を伴う。
③発達期(おおむね18歳以下)に発症。
適応行動の障害とは、日常生活において必要なコミュニケーション、身辺処理、対人及び対社会的関係、外出(交通機関や公共施設の利用等を含む)、健康や安全管理、必要なことがらの学習、余暇の活用、就労などに困難を抱える。
知的障害の程度や状態には、言語、視覚、聴覚、肢体、情緒、てんかんなどの他の心身の障害を合併、重複している例もあり多様であるが、具体的には以下のような特徴がみられる。
①読み書き計算の理解がむずかしい
②抽象的な事がらの理解がむずかしい
ものごとを的確に理解、認知する能力面が弱いために、単に口頭だけの説明や指示は通じにくい。またそのことが的はずれな言動の原因にもなり、その結果としてコミュニケーションがうまくいかない、言動が不器用で稚拙である例が多い。
③主体性が弱い
ものごとをうまく処理できないために自分に自信がもてず、自ら考えて行動することが苦手で、結果的に人に頼る傾向が強い。
④臨機応変に対応することがむずかしい
気温や季節の変化に応じた衣服の調節、身体不調時の節制や食事の加減、善悪、危険や安全などの判断がむずかしい。自閉的傾向を有する場合は同じ行動を何度も反復したり、ものごとへのこだわりも強い。
⑤感覚機能の異常(極端に敏感又は鈍感)
外界の刺激に対する反応が極端に敏感か又は鈍感な例がみられるが、それが日常の行動異常に関係している場合もある。
⑥知的な理解は苦手でも感性には鋭さがみられる(⑤との関連もある)
一般的な比較からすれば、感性という面ではむしろ豊かなように思われる例が多い。したがってその点に配慮することにより情緒的な安定を図ることができるということが考えられる。
⑦行動異常(問題行動)
問題となる行動にもいろいろあるが、知的障害の程度が重度の場合と自閉性障害が合併している場合に特に顕著となる。
主な問題行動の例を列挙すれば、自傷行動、他傷行動、固執性行動、破壊(破損)行動、奇声、うなり、大声、多動、飛び出し、寡動、徘徊、睡眠障害、拒食、異食、偏食、反芻、便いじり、便食い、夜尿、収集癖、盗癖、など
 「精神薄弱」から「知的障害」へ/発達障害・精神遅滞・知的障害の用語について 「精神薄弱」から「知的障害」へ/発達障害・精神遅滞・知的障害の用語について
 知的障害と精神障害について 知的障害と精神障害について
自 閉 症
次の三つの障害特性によって診断される。
①社会性の障害
対人・対社会的関係がうまくいかない、視線が合わない、ひとり遊びを好む、赤ん坊の場合あやされても反応が乏しいなど。
②コミュニケーションの障害
ことばの遅れやことばが出ても人称の逆転やオウム返し、独語などが顕著で会話にならない。知的障害を伴う場合はコミュニケーション能力の発達自体に問題がある。
③特有なこだわりを伴う行動障害
反復的に手をヒラヒラさせる、ピョンピョン跳ねる、身体を揺するなどの特異な常同行動、物事や順序への特異なこだわりがみられる。
常同行動とは、文字通り常に同じ行動を繰り返すことをいう。
アスペルガー症候群
自閉症にみられる特徴的な三つの症状のうちのコミュニケーションの障害はほとんどない。 言語発達や知的発達に遅れはないが、自閉症に類似した対人及び対社会的関係がうまくできない社会性の障害を有する。興味の著しい偏りやファンタジーへの没頭があり、ときには儀式的な行為がみられ、不器用さも目立つが、自閉症より発達的予後ははるかに良好である。
知能指数が100を超えるケースもあり、自閉症の場合にみられるようなある特定の分野で優れた能力を発揮する例は、アスペルガー症候群においても同様である。
広汎性発達障害(自閉症スぺクトラム)
広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)とは、自閉症と自閉症に類似の障害を包括する広義の自閉的な発達障害群の総称。その障害の内容や状態は多様であり、広汎(広範)に及ぶことから広汎性発達障害という。
最近は、自閉症の特徴に類似した社会性の障害を中心に、必ずしも知的障害を有するものではない障害グループを含めて、「自閉症スペクトラム」とも呼ばれている。
※自閉症スペクトラムとは、1996年にローナ・ウイング(自閉症の子を持つ母親でもある英国の自閉症研究者)が提唱した考え方を意味する。
自閉症には知的障害を伴わない例から重度の知的障害を伴う例まであり、高機能自閉症や自閉症に類似した知的障害を伴わないアスペルガー症候群を含めた場合に、それらの境界はあいまいであることから、それらを連続した一つのものとしてとらえる考え方で、自閉症及びそれに類似の障害を包括する広い概念である。
「高機能自閉症スペクトラム」 という場合は、知的障害を伴わない自閉症及びアスペルガー症候群をいう。
スペクトラム spectrum というのは、一つの現象の中に連続体としていくつもの要素が含まれるという意味である。 |

《学習障害(LD)》 《注意欠陥多動性障害》
学習障害(LD)
学習能力障害Learning Disabilities(又はDisorder)の頭文字をとって LD ともいわれている。
障害の特徴は、知的発達の遅れがないにもかかわらず、読む、書く、算数などの特定の分野の学習能力が極端に劣るというような発達の偏りがみられる。
学習障害の合併症に、チック、てんかん、発達性言語障害、発達性協調運動障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)、行為障害、適応障害などがみられる。
注意欠陥多動性障害(ADHD)
注意欠陥多動性障害Attention Deficit Hyperactive Disorderの頭文字をとって ADHD ともいわれている。
次の三つの基本症状が診断基準となっている。
①不注意(集中や注意持続困難、活動を順序立てて行うことが苦手、物忘れや紛失がはなはだしいなど)
②多動性(手足を落ち着きなく動かす、椅子にじっとして座っていられない、制止を振り切って走り回る、多弁、大声を出すなど極端に落ち着きのない行動)
③衝動性(周囲の状況や前後のことなど考えず、手段を選ばずに行動してしまう、順番が待てない、他人の行動に割り込むなど)
ADHDの合併症に、学習障害、発達性言語障害、発達性協調運動障害、行為障害、適応障害、気分障害、チック障害、てんかん性脳波異常がみられる。
※行為障害とは、社会規範や規則を著しく逸脱する反復的・持続的な反社会的、攻撃的、反抗的な行動パターンが特徴。
《要注意》
発達障害の要因の一部に、妊婦の飲酒や喫煙(受動喫煙を含む)が指摘されているようですが、最近の研究でもやはり、LDやADHDの一因に喫煙があるとの報告があります。
若い女性の喫煙者が増えたことと、LDやADHDが増えていることとの関連は無視できないように思います。
飲酒も要注意です。 |

《発達性言語障害》 《発達性協調運動障害》 《情緒障害》
発達性言語障害(言語発達障害)
言語能力そのものが発達しない 「言語の障害」 と、言語能力はあるがことばが話せない 「話しことばの障害」 の二つの場合があるが、臨床的にはこの二つの場合が重なっている例が多い。
言語の障害には聴覚障害、知的障害、自閉症、小児失語症などによる場合があり、これらでは、ことばだけでなく書字にも困難が生じうる。
話しことばの障害には脳性まひ、構音障害、口蓋裂、吃音などがある。
発達性協調運動障害
極端な不器用さ、ぎこちなさによって生活に支障となる問題を抱える状態をいう。
不器用さの程度や状態には発達にかかわる領域が相互に関連しあっており、生活経験を重ねることによって器用な部分が不器用な部分をカバーするというように、年長になるにつれ極端な不器用さは軽減されうる。
情緒障害
感情・情動の不安定さが著しく、自己コントロールができないために日常生活で支障が生じている状態をいう。主に心因性のもので、感情障害、情動障害、気分障害ともいわれ、成人の場合の精神疾患である神経症(ノイローゼ、ヒステリー)という診断名に相当するものと考えればよい。
しかし病気意識のない発達期にある子どもの場合には、そうした診断名は適切ではないことから「情緒障害」ということばが使われるようになった。
具体的な症例には、緘黙、孤立、登校拒否、反抗、授業妨害、怠学、チック、爪噛み、夜尿、遺尿、偏食、拒食、吃音などがある。
情緒障害と自閉症とは区別されるものであるが、実際的には自閉性障害やADHDにみられる症例との重なりがあり、情緒障害学級などの教育現場では自閉症やADHDもその対象となっている。
情緒障害の場合の行動異常は心因性のものであり、知能の障害はないか、あっても二次的なものといえる。
 発達障害と発達支援と自立支援について 発達障害と発達支援と自立支援について
 障害(者)観の変遷と障害(者)についての日本の法定義 障害(者)観の変遷と障害(者)についての日本の法定義
 文部科学省 : 特別支援教育と「発達障害」の用語について 文部科学省 : 特別支援教育と「発達障害」の用語について 厚生労働省 : 発達障害の理解のために 厚生労働省 : 発達障害の理解のために
 厚生労働省 : 障害者の範囲(PDF) 厚生労働省 : 障害者の範囲(PDF)
 厚生労働省 : 障害者の範囲定義(参考資料) 定義に関する規定の状況(PDF) 厚生労働省 : 障害者の範囲定義(参考資料) 定義に関する規定の状況(PDF)
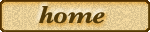
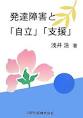
発達障害と 「自立」 「支援」 (田研出版 2007年6月発行)
A5判250頁 2750円
教育的・福祉的観点から発達支援、自立支援をめぐる問題を考える。
第1章 発達障害をどのように理解するか
発達期における「発達」の「障害」/発達と退行/発達障害の早期発見と早期対応の意義/障害の予防ということについて
第2章 発達障害の定義と障害の内容
「発達障害」の用語誕生の経緯/発達障害と精神遅滞・知的障害/アメリカ公法における発達障害の定義/
日本の法律上における発達障害の定義/発達障害の範囲と内容
第3章 発達障害と新しい障害の概念
発達障害という概念の発展/国際障害分類の試案/国際生活機能分類の考え方/新しい障害の概念と障害者福祉
第4章 人間的成長発達の特質
人間を形成するもの/人間的成長発達の量的側面と質的側面/人間的成長と“自我”の発達/他律から自律・自立へ
第5章 発達支援と自立支援
人の発達と自立について/発達支援と教育プログラム/自立支援と福祉サービス/福祉の意義と教育の意義
第6章 障害者支援の動向と課題
発達障害者支援法の施行について/障害者自立支援法の施行について/特殊教育から特別支援教育へ/古くて新しい課題
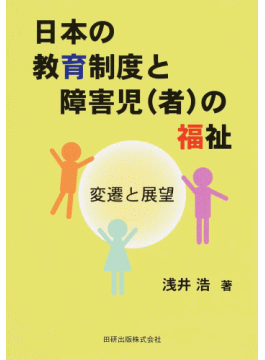
日本の障害児(者)の教育や福祉をめぐる問題、課題を考察し、今後を展望
日本の教育制度と障害児(者)の福祉
田研出版 3190円 A5判 316頁
第1章 日本の障害児教育の始まりと福祉
義務教育の制度と障害児/学校教育と福祉施設/精神薄弱者福祉法(現:知的障害者福祉法)の制定/教育を受ける権利の保障
第2章 戦後の復興から社会福祉基礎構造改革へ
社会福祉法人制度と措置委託制度/社会の変化と社会福祉基礎構造改革/「措置」から「契約」への制度転換と問題点
/社会福祉法人制度改革の意義と課題
第3章 障害者自立支援法から障害者総合支援法へ
障害者自立支援法のねらい/障害者自立支援法をめぐる問題/自立支援法から総合支援法へ/障害者総合支援法施行3年後の見直し
第4章 教育の意義と福祉の意義
人間的成長発達の特質と教育・福祉/人間的進化と発達の個人差/教育と福祉の関係/「福祉」の意味と人権
第5章 展望所感
障害(者)観と用語の問題/新たな障害(者)観と国際生活機能分類の意義/障害児教育の義務制の意義と課題
/障害者支援をめぐる問題
copyright ⓒ2012 日本の「教育と福祉」を考える all rights reserved.
|