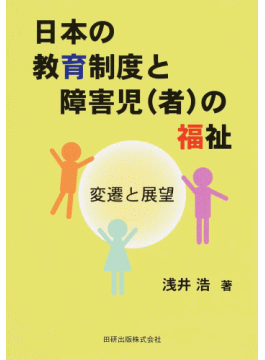障害(者)観の変遷と国際生活機能分類(ICF) 「障害」といえば、これまでは個人の身体的・精神的な欠陥や不全の問題だとする医学モデルとして捉えられてきました。それは専門的な治療の対象として治癒や改善がみられなければ、それは個人の問題であり、仕方がないとする見方や考え方であったといってよいでしょう。 そうした人々の障害(者)観は大きく変化をし、現在は、障害者も同じ生活者であるということから、人としての“生活の質”や“生活のしづらさ”にも目を向けた見方や考え方がなされるようになりました。 その背景には人権意識の高まりやノーマライゼーション思想の広がりにより、また障害をもつ人自身による自立生活運動の影響もあるわけですが、そうした変化を促す大きな転機となったのは世界保健機関(WHO)が、1980(昭和55)年に障害に関する世界共通の理解と科学的なアプローチを可能にすることを目的に作成した国際障害分類試案(ICIDH)を発表したことと、その翌年1981(昭和56)年の国際障害者年です。 国際障害分類の考え方は、 国際障害者年を契機に世界的な規模で障害(者)観に大きな影響を与えることとなりました。そしてこの国際障害分類の考え方をさらに推し進めて作成されたのが、 2001(平成13)年5月に世界保健機関(WHO)の第54回総会において採択された国際生活機能分類(ICF)です。 この国際生活機能分類(ICF)の考え方は、障害をもつ人も障害をもたない人と同じ「生活者」であるという認識を促す意味では画期的であり、障害(者)をどう理解するかの指針となる最新のものといえます。 障害(者)についての日本の法定義 日本における障害(者)観は、世界的な動向とも関連しつつ変化してきました。それに伴い障害者支援に関する考え方や取り組み方も変化して現在に至っています。 日本では、障害者福祉に関する施策の基本となる法律として 心身障害者対策基本法 が1970(昭和45)年に制定されました。その後、「国際障害者年(1981年)」、「国連・障害者の十年(1983~1992年)」などを契機とする国際的な変化の流れを受けて1993(平成5)年に心身障害者対策基本法は、「障害者基本法」に改正、改称されました。 障害者基本法は、2004(平成16)年にも改正され、さらに2011(平成23)年の改正では、2006(平成18)年に、国連で障害者権利条約(障害者の権利に関する条約)が採択されたことが大きく関係しています。 この条約に、日本も2007(平成19)年9月に外務大臣が署名し、批准に向けて国内法令の整備等を進め、2013(平成25)年12月4日に批准が正式に承認されました。条約に署名するということは、条約に賛同し、批准の意思があることを表明する行為です。条約の批准とは、国として条約に拘束されることを正式に認める(国会の承認が必要)ことです。 したがって条約の批准には国内法令との整合性を図る必要があるわけで、障害者の権利条約の批准に向けて日本の国内法制度の整備が進んだ意義は大きいと思います。障害者基本法の改正、障害者総合支援法の施行、障害者虐待防止法の施行、障害者差別解消法の施行、などは障害者権利条約との整合性を図るためでもあったわけです。しかしその実効性という点では、理念のみが先行している感があり、問題や課題も多いのが現状です。 障害者権利条約の締約国である日本の教育や福祉、労働及び雇用などが今後、実際的、具体的にどのように進展していくのか、動向を注視することが大切だと思います。 心身障害者対策基本法から障害者基本法へ 日本の障害者に関する総合的な施策の基盤が整うのは、1970(昭和45)年に「心身障害者対策基本法」が制定されてからのことです。 戦後の1949(昭和24)年に身体障害者福祉法が制定され、1960(昭和35)年に精神薄弱者福祉法(現在の知的障害者福祉法)が制定されるなど、障害者に関する諸施策が講じられるようになり、そうした各省庁が所管する諸施策の総合的な対応が必要となって制定されたのが心身障害者対策基本法です。 心身障害者対策基本法は、国及び地方公共団体の責務を明確にし、心身障害者の定義づけをしたこと、調整機関として国(厚生省)に中央心身障害者対策協議会、都道府県・指定都市に地方心身障害者対策協議会を設置したこと、などが法の意義として重要です。 心身障害者対策基本法は、障害者関係の諸施策の法制上の基本となる法律として位置づけられるものですが、世界的な動向とも関連し、1993(平成5)年に改正されて、法律名も「障害者基本法」に改称されました。その後も国際的な動向等を踏まえた改正があり、現在に至っています。 心身障害者対策基本法の制定当初の障害についての規定は、心身の機能や形態面に着目した障害の捉え方であり、精神薄弱(知的障害のこと)は法の対象に含まれているが、精神障害は法の対象には含ていませんでした。
心身障害者対策基本法から障害者基本法へ
「障害(者)」の定義の変化
《定義変化のポイント》 ①1970(昭和45)年:心身障害者対策基本法 ・心身障害=「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、 呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥」の総称 ・心身障害者=「心身障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」 ②1993(平成5)年:心身障害者対策基本法 から障害者基本法へ ・心身障害 ⇒ 「障害」 障害= 「身体障害、精神薄弱又は精神障害」の総称 ・心身障害者 ⇒ 「障害者」 障害者 =「障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」 ③2004(平成16)年: ・「精神薄弱」から「知的障害」へ 身体障害、精神薄弱又は精神障害 ⇒ 身体障害、知的障害又は精神障害 ・「長期にわたり~制限を受ける者」から「継続的に~制限を受ける者」へ 長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者 ⇒ 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者 ④2011(平成23)年:・精神障害に発達障害を含む 障害=「身体障害、知的障害又は精神障害」の総称 ⇒ 「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身機能の障害」の総称 ・「障害があるため~制限を受ける者」から「障害及び社会的障壁により~制限を受ける状態にあるものをいう」へ 障害者=「障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」 ⇒「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」 ・社会的障壁=「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣 行、観念、その他の一切のものをいう」 ※「社会的障壁」は法律上の新たな用語 障害(者)関連の現行法は、「障害者の権利条約」「障害者基本法」を踏まえたものであるわけですが、さらなる法的整備は必要だと思います。 障害(者)関連の現行法の定義 《障害者基本法》の定義 昭和四五年五月二一日 題名改正 平成5年 最新改正 平成25年 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号定めるところによる。 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他の一切のものをいう。 《身体障害者福祉法》の定義 昭和二四年一二月二六日 最新改正 平成30年 第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。 注)別表とは、身体障害者施行規則でいう「身体障害者障害程度等級表」をいう。視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害、肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、心臓、じん臓若しくは呼吸器又は又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害についての障害の程度を等級別に明示。 この表に該当しても、身体障害者手帳の交付を受けていなければ、法的には身体障害者とは認められないことになる。 《知的障害者福祉法》の定義 昭和三五年三月三一日 最新改正 平成30年 知的障害(者)についての定義規定はない。 注1)知的障害については、「身体障害者手帳」のように、手帳の所持について明文化された法律上の定めはない。 社会通念上知的障害と認められればよいということであろうが、知的障害のための「療育手帳」制度がある。療育手帳は児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に対して交付される。 療育手帳制度は身体障害者手帳のように法律に根拠は持たず、国通知による「療育手帳制度要綱」にて各県ごとに実施を図るよう指導がなされている。そのため手帳には別名の併記もある。 ≪例≫ 緑の手帳 愛の手帳(東京都は国の制度化以前の昭和42年に愛の手帳制度を制定) 注2)手帳を所持することが社会的不利へつながる場合もあることから手帳の所持を拒否する例もある。しかし実際的に支援サービスを受けるためには手帳の所持は必要。
《精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(略称:精神保健福祉法)》の定義 昭和二五年五月一日 題名改正 昭和62年 最新改正 令和元年 第5条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。 注)障害者基本法では、障害者を、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者」 としているが、この精神保健福祉法の定義では、知的障害は精神障害ということになる。 知的障害と精神障害が重複する場合はあるが、具体的な支援においては知的障害と精神障害は分けて考えたほうがよい。
第2条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発症するものとして政令で定めるものをいう。 2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。 3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。 注) 平成28年5月25日:改正発達障害者支援法が成立。 議員立法で平成17年に施行された発達障害者支援法の改正法が平成28年5月25日の参院本会議で可決、成立。 《児童福祉法》の定義 昭和二二年一二月一二日 最新改正 令和2年 第4条 ② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童をいう。 注)平成28年5月27日 : 急増する児童虐待への対応を強める改正児童福祉法が参院本会議で、全会 一致で可決、成立。
(略称:障害者総合支援法)》の定義 平成一七年一一月七日 最新改正 平成30年 第4条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者(発達障害者支援法に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。 2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。 3 この法律において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。 4 この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。 注) 障害者総合支援法の前身である障害者自立支援法の施行により、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、必要なサービスを利用しやすくするために、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する仕組みにするとして従来の障害福祉サービスの内容が再編された。 そしてサービスの必要性を明確化するということで、障害の程度を6段階に区分して認定するための「障害程度区分」の審査・判定を行う「審査会」が各市町村に設置された。しかし障害の内容は同質・一様ではないわけで、区分判定に関することが問題となり、障害者総合支援法では、「障害程度区分」は「障害支援区分」に改められて現在に至っている。 厚生労働省:障害者自立支援法の一部を改正する法律の概要(PDF)
《障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (略称:障害者虐待防止法)》の定義 平成二三年六月二四日 最新改正 平成28年 第2条 この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条に規定する障害者をいう。 2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。 3 この法律において「養護者」とは、障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等及び使用者以外のものをいう。 4~8 (略) 《障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (略称:障害者差別解消法)》の定義 平成二五年六月二六日 最新改正 令和3年 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 2 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 《障害者の雇用の促進等に関する法律(略称:障害者雇用促進法)》の定義 昭和三五年七月二五日 題名改正 昭和62年 最新改正 令和元年 第2条 一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 ニ 身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものをいう。 三 重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 四 知的障害 障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 五 重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 六 精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 七 (略) 《障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)》の定義 日本政府公定訳 (2014年1月20日公布) 第1条 目的 この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。 第2条 定義 この条約の適用上、 「意思疎通」とは、 言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。 「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。 障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む。)を含む。 「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するものではない。
|
||||||||||||