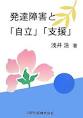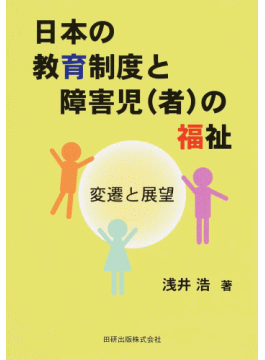|
発達障害と発達支援/自立支援 |
|
2013.3.24 更新 2015.12.18/2016.10.1/2017.7.7/2019.7.26/2020.6.12/2023.4.14 |
||
発達障害とはいっても、成長発達はしないということではありません !! 人が人として成長発達するためには、そのための支援がなければなりません。発達支援や自立支援で大切なことは、「発達」や「自立」についてどのように考えるかということです。 発達支援も自立支援も人の一生(生涯)にかかわることです !! 人の生涯を概観すれば、その成長発達や自立を支援するということは、必然的に「生活の質」や「衰退(老化)」についても考えなければならないと思います。 発達支援にしろ自立支援にしろ、それは人の生涯を見据えたものでなければならないと思います !! 実際的な支援で大切なことは、発達障害の内容やその程度・状態を把握したものであり、発達レべルに即したものであることです。
|
発達支援とは 発達障害は、日常生活又は社会生活に必要な学習、運動、言語、社会性などの発達という面での問題を抱えるわけですが、成長も発達もしないということではありません。発達支援の前提として大切なことは、どこにどのような問題があるのかをよく理解し把握することです。 発達を支援するとは、人の “生涯(ライフステージ)” を見据えたものでなければなりません。なぜならその支援は人の生き方や生きがいにかかわることであり、それは人の一生を左右するとも考えられるからです。 人の生涯を見据えるということは、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期のそれぞれをどのようにとらえるかということであり、それにより具体的な支援をどのように考えるかということです。 生涯を見据えた支援とは、人の生涯の福祉「生涯福祉」にかかわる生涯の支援「生涯支援」を意味します。 自立支援とは 一般的には、自らの力で身辺生活の処理ができ、自らの意志で職業を選択し、自らの生活を開拓し、生計を維持していけるようになれば自立した人として認めてもらえるはずです。 しかし身辺生活の処理が自力でできても、あるいは職業的にも経済的にも自立できているということであっても、その生活が常に不平不満に満ち、堕落したものであるとすれば、「生活の質」という点では、人として心ゆたかな自立生活を実現しているとはいえないと思います。 自立生活とは、突き詰めれば、その人にとって納得または満足できる生活を実現することであり、その人なりの張り合いをもち安定した気持ちで生活を維持することができるということだと思います。 つまり日常生活で介助を受け、あるいは職業的、経済的に何らかの援助を受けている場合でも、そうした支援システムが整備され、それを活用(利用)した生活が確立し、生活の拠りどころとなる居場所があり、そこでその人が精一杯生きる力を発揮し、その生活に満足または納得して、その人なりに安定した気分で生活を保持できれば、それも人の生き方であるはずです。したがってそうした状態に至るのを自立と考えてよいと思います。 自立支援の前提として大切な「自立についての考え方」をなおざりにしたまま「自立支援」が強調されているところに支援に関する問題が生じている現状があるのではないでしょうか。
他律から自律へ 人が社会生活を営んでいくには、まず、“拠りどころとなる生活の場” がなければなりません。そして自らものごとを選択し、決定し、処理するというように自主的な生活行動としての “自己規制” ができるようにならなければなりません。 自己規制とは、自分で自分の行動をコントロールすることですが、それがいわゆる「自律」です。自律的な行動ができるようになるためには、はじめは他律的な指導を必要とします。そのためにはまず自分を発揮し、それを受け止めてくれる大人の存在が重要となります。 人間的な成長ということを、 社会生活への参加のための “自律的行動” の発達というようにとらえると、そうした発達を促すためのまず第一歩は、“身辺生活の処理” ということの自律です。そのもっとも基本となるのが、食事・排泄・清潔・衣服の着脱、整理整頓などに関することです。 食事・排泄・清潔・衣服の着脱、整理整頓などに関することができるようになるということは、 単に生活に必要だからではなく、それは教育的観点からすれば、自分には何ができるのかということをわからせるところにこそきわめて重要な意味があるわけです。 なぜなら自分には何ができるかという自覚がなければ人の “やる気” というものは起きてはこないからです。やる気が起きてこなければ、生活の自律という方向に進むことはできないし、集団生活にも支障をきたすことになります。 自律から自己実現・自立へ 社会参加や自立生活に至るには、《他律 ⇒ 自律 ⇒ 自己実現 =自立》という道筋をたどることになります。 “他律” の要素として考えられるのがいわゆる「しつけ」や「教育」「指導」「訓練」などの内容や方法です。 子どものしつけや教育においては、子どもに対する大人の姿勢が大きく影響することはいうまでもありません。 “自己実現” とは、その人なりに自らの身上を受け入れ、その人なりによりよい生き方を見出し、それに納得または満足できるような、あるいは安定した気分で過ごせるような自分の生き方を実現することです。 自分の生き方や生きがいに納得または満足できるかどうか、気持ちの安定を保つことができるかどうかは、その人の感性や価値観あるいは人生観を伴う “自律” の問題です。 したがって「自律」による「自己実現」が「自立」です。そのため “自律的” な生活態度や生活意欲をいかに喚起し、養い、その持続を図るかというところが自立支援では大切となります。 発達障害の場合 発達障害の場合、自立生活の展開がどの程度可能かということは、“自律的” な生活行動がどの程度可能かどうかということが関係すると思います。 自律的な生活行動(活動)ができるようになるためには、はじめは他律的なリードが必要です。そこに「しつけ」や「教育」の果たす役割の重要性があり、具体的な自立支援に関する課題があると思います。 知的(発達)障害の場合は、その障害特性として主体性の弱さがあり、自らの生き方について自発的に思考し、ものごとを的確に判断し、自主的に行動したり、社会的資源を活用したりすることがもともと苦手です。 自閉性障害の場合は、ものごとへのこだわりや対人・対社会的な関係において問題を抱えやすいということがあります。 知的障害にしても自閉性障害にしても、その障害特性は一般の人々にはわかりにくく、理解の得られにくいものだと思います。そのため人々の理解を促す努力を要し、障害特性に配慮した継続的、長期的な支援を要することになります。
いわゆる発達期に発現する(明らかになる)障害を発達障害というわけですが、「発達期」とは、人の一生を便宜的に胎内で育つ期間も含め、胎児期、新生児期、乳・幼児期、青年期、成人期、老年(高齢)期、に区分した場合の青年期又は成人期に至るまでの期間をいいます。年齢でいえば20歳前後位までを意味します。 そもそも人の成長発達の程度や状態には個人差があるわけですから、どの程度からどの範囲を発達障害というのか、一般の人々にはわかりにくいと思います。それが発達障害の特徴でもあるといってよいかもしれません。そうした点に留意しつつ発達段階に即した支援が大切です。 <乳・幼児期> この時期は、早期発見・早期対応のためには重要な時期ですが、乳幼児健診等で障害がわかった場合に、その告知に関する問題やその告知を親や家族がどのように受け止めるかという問題があります。 したがって障害児本人に対する早期の療育的支援等とともに、その親や家族に対する支援も重要です。そのためには、乳幼児健診のあり方とともに発達障害者支援法が定めるところの「発達障害者支援センター」の果たす役割も大きいと思います。 <児童期> 児童期は、就学年齢に達する時期であり、乳幼児期における療育機関等を中心とする支援から教育機関を中心とする支援に移行することになります。 発達障害の場合、その障害を早期に発見できるとよいのですが、乳幼児期は発達の状態そのものが未熟な段階にあるために、障害とは気付かずに見過ごされる場合もあり得るわけです。したがってその点を踏まえた支援体制が重要となりますが、そのためには特別支援教育システムのさらなる整備充実に期待しなければなりません。 また児童期においては、障害をもつ子どもの兄弟姉妹との関係に配慮した支援のあり方も大切となります。 <思春期> 思春期は、もともと身体的な発達面と精神的な発達面のアンバランスな状態を抱えやすい時期です。したがって発達障害の場合もそうした点に配慮した支援を要することはいうまでもありません。 この時期は、就労に向けた意識や態度を養い、社会性を身につけるための支援とともに、心身の発達的変化に伴う性や恋愛に関する悩みなども受け止めた支援と、さらに犯罪の被害者にも加害者にもなりかねない危険性のあることにも留意した支援が大切となります。 そのためには、ものごとに対する適宜の判断力を養わなければなりませんが、それは障害の程度や状態、興味や関心のレベルに即した支援でなければならないという点で、支援の専門性を要する部分が大きいと思います。 <青年期> 人の一生を概観すると、学齢期の生活よりも学齢期を終えた以降の生活のほうがずっと長い。したがって青年期では、その後の成人期、高齢期へ向けていかに充実した生活を送ることができるかどうかということが本人にとっても親や家族にとっても重要な問題だと思います。そのため就労の場の確保や日中活動の場の確保に関する問題とともに、生活意欲を高め、もっている力を精一杯発揮できるような支援のあり方が課題となります。 またこの時期は、本人にとって一番身近な支えである親の高齢化や兄弟姉妹の生活にも変化がみられるようになり、そうした変化に配慮した支援も必要となります。そうした支援を考えた場合、そこにいわゆる障害者支援施設等における取り組みがきわめて有効であり、施設の利用者には生活の拠りどころにもなり得るものであるわけで、そこに施設の社会資源としての有用性、重要性があると思います。障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)はその点を踏まえたさらなる見直しを要する法律だと思います。 <成人期> 一般的な見方をすれば、成人期に至るということは、自らの身の回りのことは自ら処理できるようになり、一通りのものごとに関する理解力や判断力も身について、職業的にも経済的にも自立し、結婚をし、家庭を築き、社会的な役割を担い、自己の存在の確立に向けた生き方を発展させていく時期だといえます。 この時期は、就労の場や興味や能力に相応した活動の場があり、それにより日々の生活に張り合いをもって心身ともに安定した生活を送ることができ、それが持続できるよう自己研鑽に努めるとともに人間関係も豊かになるような生活の展開が理想なわけですが、発達障害の場合は、それがどの程度可能かを見きわめた支援が大切であり、無理をしないことも大切です。また親亡き後のことや兄弟姉妹との関係、本人の老後にも目を向けた支援でなければなりません。 こうした支援のためのさらなる法制度の整備を図る必要がありますが、その点で現行の成年後見制度は適切、有効とはいえない問題課題が多いと思います。 <高齢期> どんなに健康な人でも、高齢化に伴い必ず衰え、心身に変調をきたす時期がきます。発達障害の場合も当然、老化はあるわけです。そのための変調も起こります。 しかし注意を要することは、一般的な高齢化による心身の変調は発達期を経て獲得した機能や能力が失われていく状態ですが、発達障害の場合は、もともと本来の機能や能力の獲得に困難を抱えた状態で老化を迎えるわけで、そこに違いがあり、その点に配慮した対応を要します。 現行の高齢者に対する施策は、もともとは健康であった人の老化に配慮したものではあっても、発達障害の内容や状態に配慮したものとはいえません。発達障害の場合も、現行の老人関係法制度に基づいた施策、支援で問題がなければそれでよいのですが、障害の特異性に配慮した支援の必要性があるのも確かです。そこに誕生からその後の成長発達を見据えた支援の意味と課題があるわけです。 発達障害者支援法が施行された1年後に、障害者自立支援法(現:障害者総合支援法)が施行され、現在に至っています。どちらも法律名は「支援法」で障害者の支援に関わる法律ですが、その関連性及び整合性という点も含め、実情に即した見直しや再検討を要すると思います。
人間的成長発達を促すためには時間をかけ、いろいろな効果的手段を用いて発達段階を進めていくための教育的環境条件が大切となります。それは発達障害の場合であっても同じです。 障害の程度や状態に応じて、期待できそうなことや、可能性のあるところを一応のめどとして、それ以上は不可能とするのではなく、段階的に目標を定め、そこに到達することができたら次の段階へと可能性を発展させていくという考え方が大切です。その段階を一応次の5つのように考えるとよいと思います。 1)身辺生活の自立 《目指すこと》 ・基本的生活習慣 ・意思の表示 ・生活の軌道 <基本的生活習慣> 基本的生活習慣とは、食事・排泄・清潔・衣服の着脱・整理整頓等に関することで、これらのことができるようになることは人間的生活において必要だからというだけではなく、その教育的な意義は、自分はどういうことができるのかという自己の力を自覚させるところの第一歩であるというところにあるわけです。 なぜなら人の “やる気(意欲)” というようなものは自分には何ができるのかという自覚がなければ起きてはこないものだからです。生活の基本的なことについての自分の能力や、なすべきことについての自覚がなければ生活の自立という方向に進むことはできないし、集団生活に参加していくことにも支障をきたすことになります。 <意思の表示> 意思の表示とは、自分が何をしたいかを表現することですが、意思表示ができるようにならなければ、行動の自立を促進することはできないと考えます。基本的生活習慣に関するようなことは、はじめは他律的にやらされるということが多いわけですが、それが自律化していくためには行動の自己規制(セルフコントロール)ができるようにならなければなりません。 自分の意思を表すことができるようになるということは自分の行動を自律化する前提条件として重要であり、意思の表示ができない段階にとどまっているいる場合は、基本的生活習慣といわれるような行動も自らのものではなく、他律的な行動の域を出ないため、いちいち指示されないと行動できないと考えられます。 <生活の軌道> 生活の軌道とは、人間的な生活行動には目的性、一貫性がなければならないわけで、一連の行動が、ある目的達成のためのつながりをもって行われるようになることを意味します。 つまり瞬間、瞬間の刺激に対する単なる反応的行動ではなく、目的性や一貫性のある行動が自発的にとれるようになることが大切であり、そうした行動がとれるようになれば、その生活は軌道に乗ったということだと思います。 2)集団生活への参加 《目指すこと》 ・自分と他人との関係の理解 ・集団生活の規則の理解 ・ゲームのルールの理解 仲間集団でのゲーム遊びとか競争や共同制作などを介した指導により、ルールの理解や自分と他人との関係の理解ができるようになれば、それは自己統制力を養うことにつながります。ゲームのルールの理解は、集団生活のルールの理解にもつながります。 したがってゲームやルールの工夫は教育的要素としてきわめて重要です。また集団内で適当な位置や役割が得られるようになれば情緒的にも安定し、それだけもっている能力が発揮できるようになり、それが知的発達を促進することにもなります。 集団生活に入っていくためには、自分と他人との関係の理解ができるようになり、意思の交換ができるようにならなければなりません。そこにコミュニケーション能力をいかに養うかということがあるわけですが、それには言語の発達が関係します。しかし言語の発達といってもそれは言葉が出なければだめだというものではありません。そこに教育的指導上の専門性があるわけです。 3)社会生活の理解と参加 《目指すこと》 ・学校生活の理解 ・家庭生活の理解 ・社会への関心 ・自然への関心 ・地域社会の理解 ・地理的歴史的理解 集団生活への参加を通して対人関係が発展するとともに、それが社会生活の理解と参加につながります。この場合の社会生活とは、学校生活、家庭生活、地域社会での生活を意味しますが、それぞれにおける生活(行動)のルールを可能な限り理解できるよう、またその一員としての行動がとれるような指導が大切となります。 学校生活でのルールなどは、毎日の学校生活を通して習得していきますが、家庭生活とか地域社会での生活となると、個々の子どもによって違いがあることに対する配慮を要します。それぞれの生活領域の拡大ということを考えながら、生活に関する関心を深めていくような指導が大切ですが、そのためには、家庭におけるお手伝いなどを取り入れていくことが効果的ですし、買い物学習などの実際的、具体的な学習活動が効果的です。 こうした実際的、具体的な学習活動を通して、どのような段階を経て高い理解に達するかを系統的に見てゆくことがさらなる教育的指導上の課題となると思います。 4)生活の常識と技術の習得 《目指すこと》 ・度量衡 ・時間暦 ・天候 ・保健衛生 ・交通 ・経済生活 生活の常識とか生活に必要な技術の習得ということは、教科学習的な方法よりもいろいろな行事や現実度の高い活動などによって体験的に学習することが効果的であることは確かです。 特に知的発達に障害のある場合などは、障害の程度や状態を把握し、教科学習的方法に偏らない配慮が大切であり、現実度の高い体験や日常生活に即した指導方法を工夫することがもっとも効果的な支援となります。 5)働く人としての自覚と行動 《目指すこと》 ・遊びと仕事の分化 ・働く意欲(仕事意識)の高揚 ・働く態度の形成 ・仕事の内容の理解 働くことの意味や大切さを理解させ、働く意欲や態度を養うためには、生活の常識とか生活に必要な技術の習得ということと同じように、教科学習的方法よりも、いろいろな行事や現実度の高い作業活動や協同制作(共同作業)などの活動を通した体験的学習が効果的です。 知的障害の程度や状態が重度であるほど教科学習的方法は効果的とはいえません。それは普通一般的にみても、知識や技術的なことはそれのみを単独に取り上げて、むやみに習得させようとしても、それは身につきにくいものといえるからです。 ただし知的発達に障害のない場合は、そうしたことに対する自ら努力するという力が備わっているので、年齢的な成長や経験を通して、あるいは必要に応じて習得も可能なわけです。 例えば、少年時代にはかなりの怠け者であったとしても、大人になって働き者になり、目的意識をもってきちんとした生活の技術を身につけるというようなことはあり得るわけです。それは知的な面の障害がなく、発達に障害がなければ、生活経験を重ねる中で、生活に必要ないろいろなことがそれなりに育っているからですが、知的発達に障害があり、その程度が重いなどの場合、教育的働きかけがなければそうした働く意欲や態度は育ってはこないと思います。
「発達保障」と「生涯発達」について 人として生まれたならば、人として成長発達する権利は誰もが有するわけですから、その発達は保障されなければなりません。それが「発達保障」という考え方だと思います。 人には寿命があります。誰もが成長発達の時期を経てやがて衰え、終焉を迎えるにもかかわらず、「生涯発達」などといわれています。それは人それぞれが、その一生を通して人としてのよりよい生き方の実現を目指すということだと思います。そうした一人ひとりが目指す努力とそのための支援の積み重ねは単なる個人の一生の範囲を超えて、人の社会の更なる繁栄・発展へと向かうということだと思います。 要するに、一人ひとりのよりよい発達が、よりよい社会の発展になるはずです。そこに「発達保障」「生涯発達」の意味と課題があるはずです。発達支援とはそうした意味と課題を踏まえたものでなければならないと思います。 人の生涯を見据えた「生涯支援」について 人の一生を概観すれば、定年後や老後の生活をどのように送るかということは、人生においては重要なことだと思います。発達に障害のある人を支援することにおいても、その支援は、生涯を見据えたものでなければなりません。 発達支援にしろ、自立支援にしろ、それは要するに、人の暮らし方や「生活の質」にかかわるものであるという理解認識が大切です。 人の一生を考えた場合、必ず成長発達の時期があり、そうした発達期を経て老化(衰退)へと向かいます。したがって発達支援にしても自立支援にしても、それはその老後にも配慮した支援でなければなりません。しかし障害者の支援の現状は、そうした配慮を含めた体系的な支援体制が未確立のままであるといっても過言ではありません。 「支援」ということばが飛び交っている昨今ですが、障害者支援においては人の生涯を見据えた支援の大切さということの認識が足りないように思います。
|