
|
発達障害の早期発見・早期対応について
≪出生前診断の意義と問題≫
2015.2.24/2016.12.2/2017.5.10/2019.8.30/2020.6.27/2020.11.3/2021.11.21/2022.9.17
/2024.11.30 |
 |
 |
発達障害の早期発見と早期対応の意義
人間的成長発達が促進される発達期において、知能、運動、言語、行動、学習、社会性などの健やかな発達という面での問題が顕在化するのが発達障害です。それを早期に発見し、早期に対応することがきわめて大切なことになります。
なぜ早期に発見し、早期に対応することが大切かといえば、成長発達の段階で障害を受けた場合は、それがその後の人間形成に影響を及ぼすことになるからです。
したがって早期に発見することにより、よりよい発達への方向性を見出すための早期対応が重要となるわけですが、それには早期発見・早期対応のための方策が講じられなければなりません。
日本の場合は、発達の程度や状態に即した早期療育等の対応が大切であることから、そのための施策として「母子保健法」に基づく取り組みがあります。
母子保健法(最新改正 平成28年)は、国及び地方公共団体の責務として、「母性や乳幼児の健康の保持及び増進に努めなければならない」 として、
また市町村は幼児の「健康診査を行わなければならない」として、「満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」の健康診査の実施を定めています。
こうした法律に基づく健康診査の実施と合わせて発達にかかわる相談事業も行われていますが、 さらなる施策の整備充実が図られていくことに期待したいと思います。
早期発見に関する諸問題
生命の誕生や生命の維持・発展にかかわる近年の医療技術等の進歩には目覚ましいものがあります。しかしその一方においては、不妊治療のためのいわゆる「生殖医療」や生まれる前の段階での胎児の病気や障害の有無、母体の状況などを調べるための「出生前診断」に関する問題があります。
出生前診断の目的には、胎児期における治療的処置の必要性への対応、分娩方法や出生後のケアや妊娠の継続にかかわる情報提供などがあるわけですが、仮に、出生前診断で胎児に異常があるとわかった場合に、その診断結果をどのように告知するか、あるいはそれをどのように受け止めるかの問題があります。
妊娠と出産は個人の権利であり、その選択と最終決定は妊婦自身に委ねられることになります。胎児に異常が認められる場合にそれをそのまま受け入れ出産するとすれば、出産後の養育の問題やその子自身の将来的な自立生活の可能性にかかわる問題等も含め、そうしたことに対する不安や相談に対する支援体制が整備され、その充実が図られているかどうかの問題があると思います。
また胎児の段階での治療の可能性に期待するという場合であっても、胎児のための治療が母体に負担を強いるような危険を伴うとしたらどうするかという問題もあると思います。
現行法上は、胎児には法的な人権はなく、胎児の命を優先させるのか、母体の命を優先させるのか、胎児の生きる権利は誰が守るのかという問題もあります。
さらに早期発見には、病気を予防するということと同じように、障害を予防するということがあるわけですが、早期発見のための出生前診断の結果が胎児の病気や障害を理由とする人工妊娠中絶につながるとすれば、それはこれから生まれてこようとする生命の意図的な排除であり、障害をもつ人の生きる権利を否定するような障害(者)観にかかわる重大な問題があります。
「障害を予防する」という場合、それは人にとって障害となるものを予防するという意味ですが、障害をもつ人の存在をも否定することのように曲解されることばの問題もあるようです。
はたして「障害の予防」という考え方は、障害をもつ人の生きる権利を保障することとは相反することであり、障害をもつ人の生きる権利を否定することになるのかという問題があるわけですが、障害者基本法の第3章第31条は次のように規定しています。
障害者基本法 (最新改正 平成25年)
第 3 章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策
第31条 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病及びその予防に関する調査及び研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の原因となる傷病の予防のため、必要な知識の普及、母子保健法等の保健対策の強化、当該傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害の原因となる難病等の予防及び治療が困難であることに鑑み、障害の原因となる難病等の調査及び研究を推進するとともに、難病等に係る障害者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めなければならない。
|
障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策として規定する障害者基本法第31条の具現化とその充実には国及び地方公共団体の責務としての力量が問われるわけですが、現状は課題も多いと思います。
<参考資料 朝日新聞>
 発達障害をどのように理解するか 発達障害をどのように理解するか
 発達障害の内容と範囲について 発達障害の内容と範囲について
 発達障害と発達支援・自立支援について 発達障害と発達支援・自立支援について
 発達障害と特別支援教育について 発達障害と特別支援教育について
 「障害」の予防について 「障害」の予防について
 「障害者」という用語問題 「障害者」という用語問題
 優生思想と強制不妊手術の実態 優生思想と強制不妊手術の実態
 障害児者に関する相談窓口 障害児者に関する相談窓口
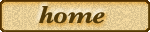
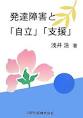
○浅井 浩 著 : 発達障害と 「自立」 「支援」 (田研出版 2007年6月発行)
A5判250頁 2750円
教育的・福祉的観点から発達支援、自立支援をめぐる問題を考える。
第1章 発達障害をどのように理解するか
発達期における「発達」の「障害」/発達と退行/発達障害の早期発見と早期対応の意義/障害の予防ということについて
第2章 発達障害の定義と障害の内容
「発達障害」の用語誕生の経緯/発達障害と精神遅滞・知的障害/アメリカ公法における発達障害の定義/
日本の法律上における発達障害の定義/発達障害の範囲と内容
第3章 発達障害と新しい障害の概念
発達障害という概念の発展/国際障害分類の試案/国際生活機能分類の考え方/新しい障害の概念と障害者福祉
第4章 人間的成長発達の特質
人間を形成するもの/人間的成長発達の量的側面と質的側面/人間的成長と“自我”の発達/他律から自律・自立へ
第5章 発達支援と自立支援
人の発達と自立について/発達支援と教育プログラム/自立支援と福祉サービス/福祉の意義と教育の意義
第6章 障害者支援の動向と課題
発達障害者支援法の施行について/障害者自立支援法の施行について/特殊教育から特別支援教育へ/古くて新しい課題
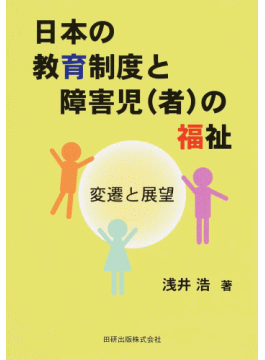
日本の障害児(者)の教育や福祉をめぐる問題、課題を考察し、今後を展望
田研出版 3190円 A5判 316頁
copyright ⓒ2012 日本の「教育と福祉」を考える all rights reserved.
|