人としてよく育ち、よく生きるための教育であるならば、障害をもつ子どもの教育も、障害のない子どもの教育も、その教育目標は一つです。
しかし障害児(者)にとって効果的な教育内容や方法を具体的に考えるということでは、その障害の内容や程度や状態に配慮することが大切であり、成長発達段階に即したものでなければなりません。
障害児(者)の教育を受ける権利を保障するからには、障害の内容やその程度や状態に配慮した教育内容や教育方法等の諸条件が整っていなければならないし、教育を受ける機会や場が用意されていなければなりません。
それは教育を受ける権利に対する教育を受けさせる義務を意味します。
教育を受ける権利の保障と特別支援教育
ノーマライゼーションとインクルーシブ教育
教育の機会均等について
学校教育法でいう 「準ずる教育」 とは
「特別支援教育」はなぜ必要なのか
障害者差別解消法の施行と大学の対応
不登校対策をめぐって
教育を受ける権利の保障と特別支援教育
日本の教育制度は、原則として障害の有無で教育を受ける場としての学校を分けてきましたが、2007(平成19)年4月1日から「学校教育法等の一部を改正する法律」によって、従来の盲(もう)学校・聾(ろう)学校・養護学校という障害種別による学校の区分をなくして、特別な教育的ニーズを抱えるいわゆる「発達障害」も支援の対象に含めた特別支援教育のための「特別支援学校」の制度が始まりました。
特別支援教育をどのように充実発展させるか、そのための教育的環境条件をどのように整えていくかは、今日的な、きわめて重要な課題です。障害種別の区分をなくすというのは、障害の内容等には関係なく誰もが教育を受けられるようにするということであって、障害の内容やその程度や状態等への配慮を何もせずに、単に一緒に学ばせるということではないのですが、そこに誤解と混乱が生じているのではないでしょうか。
教育といえば、一般的には、いわゆる読み書き算数の能力を重視し、そうしたことを教えることが大切だとする教科学習的な教育方法論への執着や知育偏重が根強くあるようです。むろんそうした能力を発揮できるようにすることは教育的な部分としては大切であり、必要であることはいうまでもありません。
しかし障害の内容やその程度や状態によっては、教科学習的な教育の内容や方法では、それを理解することがむずかしいということもあるわけです。その場合、単に教科主義的教育の内容や方法を強いるのではない教育的な配慮を要します。そこに特別支援教育の意味があると思います。
 特別支援教育について:文部科学省 特別支援教育について:文部科学省
 合理的配慮について:文部科学省 合理的配慮について:文部科学省
ノーマライゼーションとインクルーシブ教育
ノーマライゼーション理念によるところの「共に学ぶ」という考え方の方向性はよいとしても、それは障害児(者)を対象とした専門的な教育の取り組みを否定するものであってはならないはずです。
しかしノーマライゼーションの理念が、すべての子どもを普通の学校又は普通の学級へと主張し、障害児を対象にした養護学校や障害児学級そのものを否定するような運動に結びついてきた経緯があります。
現在、教育の分野では障害児の教育を、いわゆる地域の普通の学校や学級に統合して行うというインテグレーション(統合教育)をさらに発展させた考え方であるインクルージョンがノーマライゼーションと並ぶ新たな理念となっています。
インクルージョンとは、「包み込む」という意味で、それは障害をもつ人を含め、さまざまな違いを認め合い、障害をもつ人ももたない人も、共に学ぶ社会を目指すということであり、教育の分野におけるその具現化がインクルーシブ教育です。
それはすべての子どもが地域社会の学校教育の場に包み込まれ、それぞれに必要な教育が受けられるようにすることを意味しますが、教育を受ける権利で大切なことは、どのような教育をどのような方法で、どのような教育的環境条件の下で受けることができるかどうかということです。
「一人ひとりを大切にした教育」ということがいわれていますが、そこで重要なことは、一人ひとりに対して具体的にどのように対応していくかということです。
教育の機会均等について
日本国憲法の第26条には、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」とあります。
教育基本法の第4条には「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、~」「国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。」と定めています。
憲法の、「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける」「普通教育を受けさせる義務」ということと、教育基本法に定める「その障害の状態に応じ」ということは、教育を受ける権利の保障の問題を考える上できわめて重要な点だと思います。
「その能力に応じ」というのは、能力的個人差や能力的発達の程度や状態に応じるということであり、「その障害の状態に応じ」というのは、その障害の内容や程度・状態に応じることであるわけですから、その場合の「ひとしく」というのは、教育の内容や方法が教育を受ける人すべてに、まったく同じであればよいということではなく、また同じことを強要するものでもないはずです。
つまり「ひとしく」というのは、「一律に」ということとは違うということです。
また「普通教育」とは、どのような教育内容をいうのか漠然としていますが、それは一応、人としてあるいは社会の構成員として生活していくうえで必要な教育だとか、次代を担うために必要な教育だと解釈すれば、それは文化レベルや生活習慣あるいはその時代状況など社会的環境条件との関連で相対的に考えられるものだということになります。
しかもその教育の内容や方法は、教育を受ける権利を有する側によって考えられるのではなく、教育を受けさせる義務を負う側の価値観や判断基準に基づいて考えられるものだということになります。まさに学校教育における教育内容や方法はそういうことになります。その点でどのような教育の内容や方法を考えるかということがきわめて重要なことになるわけですが、ひとしく教育を受けさせるということと、一律的・画一的な教育を受けさせるということが無差別平等論の下に混同されているように思います。
教育の分野では今、障害児の教育を地域の普通の学校や学級に統合して行うインテグレーション(統合教育)を発展させた考え方であるインクルージョンがノーマライゼーションと並ぶ新たな理念となっているわけですが、それは教育を受ける権利ということからすれば、多様な障害の内容や状態等に応じた多様な教育の内容や方法があり、多様な教育の場が用意されていなければならないということであって、それは権利に対する義務です。そしてそれが本来の教育の機会均等ということであるはずです。
いろいろあってよいはずであり、多様化の時代などといわれているにもかかわらず、みんな同じ教育の場で、同じ教育の内容や方法、ということにこだわるところに混乱が生じている現状があるように思います。
学校教育法でいう 「準ずる教育」 とは
学校教育法の第72条に特別支援学校の目的として、「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。」とあります。
この学校教育法でいう「幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施す」ということをどのように考えるかということも重要な問題だと思います。
準ずる教育という言い方は、障害のない子どもの教育になぞらえるということであり、端的にいえば、同じようにするとか似せるということだと思います。
同じようにするとか似せるということで何も問題がないのであれば、わざわざ「準ずる」などと紛らわしい言い回しをせずに、最初から「同じ教育」といえばよいはずです。しかしいわゆる一般的な学校と同じでは問題があるからこそ教育のための特別な支援を行うという意味で「特別支援教育」、「特別支援学校」というのだと思います。
特別な教育支援を行うというのであれば、その学校での具体的な教育の内容や方法は、一般的な学校に「準ずる教育」ではなく、障害の状態等に応じた「適切な教育」を行うということでなければならないと思います。
「準ずる教育」から「適切な教育」に改めることにより、特別支援学校での具体的な教育的支援の方向性やそのための教育の内容や方法が考えやすくなり、工夫もしやすくなるはずです。
特別支援教育が必要だとするならば、その前提として重要なことは何よりもまずその対象となる児童生徒の実態の把握と、そのためにどのような教育をどのように行うかということを考えなければなりません。そうでなければ特別支援と称する教育の内容や方法を具体的に追求していくことにはならないからです。当然そうしたことで現在に至っているのかもしれませんが、「準ずる教育」へのこだわりはなぜか根強いようです。
障害のない児童や生徒を対象にしたいわゆる普通教育とまったく同じような内容や方法では無理があるわけですが、そうしたことの理解認識が正しくなされないまま、未消化のままの人権論や無差別平等論、ノーマライゼーションやインクルージョンなどの論理に翻弄されてしまっているようなところがあるのではないでしょうか。
準ずる教育による混乱とそれによる弊害を招かないためにも、また教育的意義や教育的効果の点からも、教育を受ける権利に対する教育を受けさせる義務という点からも「準ずる教育」は「適切な教育」に改めるべきではないかと考えます。
「特別支援教育」はなぜ必要なのか
「~、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする」というのは、単なる建て前論的な作文であるならばそれでもよいかもしれません。
しかし、「学習上又は生活上の困難を克服して自立を図る」という、その自立とはどのような自立を意味するのか、それが実はきわめて重要なことなのですが、なぜかその点の具体的な考え方がなおざりにされたまま現在に至っているといっても過言ではありません。
特別支援教育は、教育を受ける権利を有する児童や生徒のためにあるはずです。誰のための、何のための教育か、特別支援教育と称する意味は何か、ということを改めて考え直してみる必要があるように思います。
戦後日本の教育施策として障害児の学校教育が義務制になったのはよいと思います。しかし学校を卒業後の就労や日々の生活、さらにその老後に至る「親亡き後」の暮らしを概観すれば、その道筋は依然として整備されているとはいえません。
障害をどのように受容し、学校卒業後の生活をどのように見据え、そのための教育をどのように考えるか、ということが大切なわけですが、どのように暮らす(暮らせる)かの道筋が見えてこそ具体的な教育の目標や教育の内容や方法が考えられることだと思います。
1979(昭和54)年に養護学校の義務制が実施されてからのこれまでの教育の内容や方法論をめぐる諸問題及び学校卒業後の諸問題を直視し、今一度、障害児(者)の教育や福祉について原点に立ち返って考え直してみる必要があると思います。
 日本の障害児(者)の教育と福祉 日本の障害児(者)の教育と福祉
 発達障害と特別支援教育について 発達障害と特別支援教育について
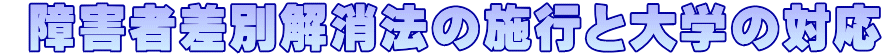
障害者差別解消法の施行で、入試や授業についても、障害者への「合理的配慮」が求められています。
発達障害 大学で支援
全大学の半数超に在籍 朝日新聞 2012(平成24)年7月4日
発達障害の学生が学ぶ機会を確保するため、大学が支援に取り組み始めている。日本学生支援機構の2011年の調査では、発達障害の学生が在籍する大学が、初めて全大学の半数を超えた。2人に1人が大学に進む時代になり、学生が多様化してきたことが背景にある。
支援機構の調査では、大学院を含む全学生約302万人のうち、発達障害の診断書があるのは1179人。診断書はないものも含め何らかの教育上の配慮を受けている学生は2918人にのぼった。発達障害の学生がいる大学は455校で全体の58.6%で、5割を超えた。
何らかの支援をしている大学は371校で47.8%。内容は多い順に①休憩室の確保②学生に合わせて実技や実習に配慮する③授業などの注意事項を文書できめ細かに伝達する④教室の座席位置などへの配慮⑤講義内容の録音を許可する⑥期末試験時間などの延長、別室受験―だった。
発達障害の支援教育に詳しい信州大の高橋知音教授は「高校までと違い、大学は授業の選択から始まる。ここでつまずき、初めて問題が顕在化するケースが少なくない。他学生と同じ条件で学ぶ機会、権利を保障するのが大事」と話している。
2005年施行の発達障害者支援法では、大学や高専に「障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をする」ことが規定されている。
 文部科学省 : 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)平成24年12月 文部科学省 : 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第一次まとめ)平成24年12月
 文部科学省 : 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ) 平成29年3月 文部科学省 : 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第二次まとめ) 平成29年3月
 文部科学省 : 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ) 令和6年3月 文部科学省 : 障がいのある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ) 令和6年3月
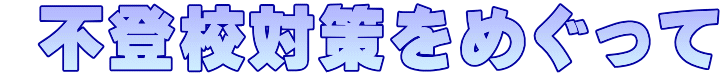
◆教育機会確保法 不登校対策で終わるな 朝日新聞 社説 2016(平成28)年12月13日
フリースクールをはじめ、学校の枠にしばられない多様な学びを正式な制度として親や子が選びとる道は、結局認められなかった。議員立法による「教育機会確保法」が成立した。
安倍首相が2年前にフリースクールを訪問し、超党派の議員連盟が法律づくりの準備を始めて機運が盛り上がったはずだった。だが、議論の過程で中身は大きく変わってしまった。
当初検討されたのは、フリースクールや自宅での学習を前提に、保護者が「個別学習計画」をつくり、教育委員会の認定を受ければ、義務教育を修了したと認める仕組みだった。
ところが「不登校を助長する」などと自民党内から異論が出て、骨抜きになった。代わりに法律に盛り込まれたのは、学校復帰を指導する自治体の「教育支援センター」や特別編成のカリキュラムの「不登校特例校」の整備など、現に行われている施策ばかりだ。
単なる不登校対策法といっていい。今の制度や対策に限界があるからこそ、新規の立法をめざしたのではなかったか。それでも状況を変える芽がまったくないわけではない。
法律は、学校以外の場で行う「多様で適切な学習活動」の重要性を認め、つらいときは学校を休んでもよいと「休養の必要性」を明記した。子どもの発達や参加の権利を保障する「子どもの権利条約」の趣旨にのっとることも、冒頭で宣言した。
文科省はこの法律にもとづき「基本指針」をつくる。どんな内容にするのか。民間団体の意見もていねいに聞きとり、公立だけでなく民間の施設やそこに通う子、自宅で過ごしている子もしっかり支える姿勢を打ち出すべきだ。
不登校の小中学生は12万6千人もいる。だがいまの法体系では、子どもが教育を受ける権利は学校で保障するしかない。法と現実との隔たりを放置し続けるのは、もはや許されない。
今回の法律制定で終わらせるのではなく、学校以外の学びをどこまで認め、それを公教育の中にどう位置づけるか、引き続き議論を深めねばならない。外国では、芸術の要素を採り入れたシュタイナー教育や、生徒らがルールをつくり、何を学ぶかを自主的に決めるサドベリー教育などが認知されている。そうした場から生まれる多様な価値観は、柔軟でたくましい社会を生む効果をあわせもつ。
法律には施行3年後の見直し規定もある。この成立を新たな検討の出発点としたい。
 文部科学省: 文部科学省:
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について(通知) 平成28年12月22日
◆いじめ把握 低学年化
17年度41万件 不登校も最多 朝日新聞 2018(平成30)年10月26日 (1面)
全国の小中高校などで2017年度に41万4378件のいじめが把握され、前年度から約9万件増えて過去最多となったことが文部科学省の調査で分かった。特に小学校低学年で増加しており、小さなトラブルでもいじめとして把握し、早期対応することを学校に求めていることなどが影響しているとみられる。また、年間30日以上欠席し、「不登校」と判断された小中学生は計14万4031人で、前年度より約1万人増え、やはり過去最多だった。
◆子どもの現実 把握半ば 朝日新聞 2018(平成30)年10月26日 (2面)
昨年度に全国で不登校の小中学生と、小中高校などが把握したいじめはともに過去最多と文部科学省が発表した。解釈や、学校現場の意識の変化の影響が指摘される一方、低年齢化を懸念する声もある。(円山史、宮坂麻子、上野創)
不登校 5年連続増加 学校以外の居場所拡大
小中学生の不登校はこの5年間、増加を続け、文部科学省の調査で過去最多(2017年度)。中学生より小学生の増加が大きく、小学生の不登校は1千人あたり5.4人で10年前に比べて1.59倍になった。中部地方の公立小で校長を務める50代の男性によると、かつての勤務校で、不登校になった後、フリースクールなどを経て、高卒認定試験を受ける子もいた。以前は学校へ戻すことが良いとされたが、今はそんな時代ではないと思う。子どもの幸せが何かを考えながら、フリースクールなど学校以外の選択肢があることも提案していきたい。
2017年に教育機会確保法が施行されたこともあり、学校以外の学びの場や居場所が選択肢の一つとして広がってきている。
いじめ認知 最多の41万件 自治体で差 実態どこまで
いじめが最多となったことについて、いじめ問題を研究している折出健二・愛知教育大名誉教授は「細かい事案も調査対象になることが周知された結果だろう」と分析する。
関東地方の公立小学校に勤める女性教諭によると、学校にほぼ毎日、「うちの子がたたかれたといっている」などと、保護者からトラブルを訴える電話が入る。
そのたびに担任は、本人や相手の児童と個別面談し、学級のほかの子からも話を聞く。「1回たたかれただけでも、『謝ってくれず、ずっと嫌だと思っている』などと訴えがあれば、いじめとして調査し、件数にあげざるを得ない実態がある」。1千人あたりのいじめの認知件数は、自治体によって差が出た。ただ、この数字が本当に現状を反映しているかは不透明だ。
一方、折出名誉教授は「友達作りの経験の乏しい子が増えていることは事実。先生も授業を行うことで精いっぱい。他者との違いを受け止めるための指導や、子ども主体の学級づくりに手が回っていないことが、近年の初等教育の大きな課題だ」と指摘する。
自殺17年度250人 警察統計と開き
文科省によると、17年度に自殺した小中高生は250人。これに対し、警察庁の統計では341人で、91人の差があった。
警察は捜査などによって自殺かどうか判断する。一方、文科省は学校側からの報告が基本。同省は「自治体に捜査権はなく、踏み込むことは難しい」と話し、具体例として「保護者が病死だと主張する場合」などを挙げる。
学校の認識のずれによって、自殺の把握が遅れるケースもある。東日本の自治体では5年ほど前、中学生の男子生徒が自殺した。今年まとめられた報告書によると、学校関係者は警察から死因について直接的な説明を受けず「(警察は)それはいえないということだった。お母さんにもそれは聞けない」としていた。
報告書によると、警察などとのやりとりから職員は、事故で亡くなったと受け止め、自殺するとは思わなかったことから、教育委員会にもそのように報告した。原因究明を求めた遺族代理人から伝えられ、自殺だと知ったのは、生徒が亡くなった約1年半後だった。
NPO法人「ライフリンク」の清水康之代表は「都道府県警と教育委員会、さらに福祉部門が別々の情報に基づいて動くようでは、効果的な自殺対策はとれない。特に、学校側が把握していなければ、他の子どもや遺族への適切な支援や再発防止策につながらない」と指摘。「縦割りを排し、情報を共有して多角的に対応する必要がある」と訴える。
◆復学意思なくても「出席」
不登校生の学校外学習 文科省が通知 朝日新聞 2019(令和元)年10月26日
不登校の小中学生が全国で約16万5千人と増え続けていることなどを受けて、文部科学省は、従来の学校復帰を前提とした支援のあり方の見直しに乗り出す。フリースクールなど学外の施設に通う不登校生を「出席」扱いにしやすくする通知を、25日付で全国の教育委員会に出した。復学のみを目標にしがちだっ教育現場の意識改革につなげる狙いがある。
不登校生には、行政が支援する教育支援センターや民間のフリースクールなど学校外で学ぶ児童・生徒も多い。これまでも所属する学校長の判断でこうした子どもを出席扱いとする制度があった。ただ、文科省は、過去に出席扱いする条件として「学校復帰が前提」と解釈できる通知を出しており、学校に戻る意思がないと適用されないこともあった。「出席」扱いになったのは約2万3千人(2018年度)にとどまる。
不登校で「欠席」が増えると、受験などで不利な扱いを受けることもあるほか、教育関係者から「登校圧力が子どものストレスになる」などと指摘があった。16年に成立した「教育機会確保法」では、学校外の多様な学びの場を支援する方針が盛り込まれ、「無理に登校する必要はない」という認識が広がりつつある。
文科省幹部は「休養が必要な子どもには無理強いはせず、将来的に本人が復学を希望したときは円滑に戻れるような環境づくりをしてほしい」としている。
(矢島大輔、山下知子)
 文部科学省:「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日 文部科学省:「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
元文科初第698号
令和元年10月25日
各都道府県教育委員会教育長 殿
各指定都市教育委員会教育長 殿
各都道府県知事 殿
附属学校を置く各国公立大学法人学長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長 殿
文部科学省初等中等教育局長
丸山 洋司
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
不登校児童生徒への支援につきましては,関係者において様々な努力がなされ,児童生徒の社会的自立に向けた支援が行われてきたところですが,不登校児童生徒数は依然として高水準で推移しており,生徒指導上の喫緊の課題となっております。
こうした中,「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下「法」という。)が平成28年12月14日に公布され,平成29年2月14日に施行されました(ただし,法第4章は公布の日から施行。)。
これを受け,文部科学省におきましては,法第7条に基づき,平成29年3月31日,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を策定したところです。
さらに,法の附則に基づき,平成30年12月から「不登校に関する調査研究協力者会議」及び「フリースクール等に関する検討会議」において法の施行状況について検討を行い,令和元年6月21日に議論をとりまとめました。
本通知は,今回の議論のとりまとめの過程等において,過去の不登校施策に関する通知における不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに係る記述について,法や基本指針の趣旨との関係性について誤解を生じるおそれがあるとの指摘があったことから,当該記述を含め,これまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し,まとめたものです。文部科学省としては,今回の議論のとりまとめを踏まえ,今後更に施策の充実に取り組むこととしておりますが,貴職におかれましても,教職員研修等を通じ,全ての教職員が法や基本指針の理解を深め,個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援等を行うことができるよう努めるとともに,下記により不登校児童生徒に対する教育機会の確保等に関する施策の推進を図っていただくようお願いします。
また,都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して,都道府県知事にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して,附属学校を置く国公立大学法人の長にあっては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して,この趣旨について周知を図るとともに,適切な対応がなされるよう御指導をお願いします。
なお,「登校拒否問題への対応について」(平成4年9月24日付け文部省初等中等教育局長通知),「不登校への対応の在り方について」(平成15年5月16日付け文部科学省初等中等教育局長通知),「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」(平成17年7月6日付け文部科学省初等中等教育局長通知)及び「不登校児童生徒への支援の在り方について」(平成28年9月14日付け文部科学省初等中等教育局長通知)については本通知をもって廃止します。
記
1 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方
(1)支援の視点
不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。また,児童生徒によっては,不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で,学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。
(2)学校教育の意義・役割
特に義務教育段階の学校は,各個人の有する能力を伸ばしつつ,社会において自立的に生きる基礎を養うとともに,国家・社会の形成者として必要とされる基本的な資質を培うことを目的としており,その役割は極めて大きいことから,学校教育の一層の充実を図るための取組が重要であること。また,不登校児童生徒への支援については児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し,学校関係者や家庭,必要に応じて関係機関が情報共有し,組織的・計画的な,個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定することや,社会的自立へ向けて進路の選択肢を広げる支援をすることが重要であること。さらに,既存の学校教育になじめない児童生徒については,学校としてどのように受け入れていくかを検討し,なじめない要因の解消に努める必要があること。
また,児童生徒の才能や能力に応じて,それぞれの可能性を伸ばせるよう,本人の希望を尊重した上で,場合によっては,教育支援センターや不登校特例校,ICTを活用した学習支援,フリースクール,中学校夜間学級(以下,「夜間中学」という。)での受入れなど,様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行うこと。
その際,フリースクールなどの民間施設やNPO等と積極的に連携し,相互に協力・補完することの意義は大きいこと。
(3)不登校の理由に応じた働き掛けや関わりの重要性
不登校児童生徒が,主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう,児童生徒自身を見守りつつ,不登校のきっかけや継続理由に応じて,その環境づくりのために適切な支援や働き掛けを行う必要があること。
(4)家庭への支援
家庭教育は全ての教育の出発点であり,不登校児童生徒の保護者の個々の状況に応じた働き掛けを行うことが重要であること。また,不登校の要因・背景によっては,福祉や医療機関等と連携し,家庭の状況を正確に把握した上で適切な支援や働き掛けを行う必要があるため,家庭と学校,関係機関の連携を図ることが不可欠であること。その際,保護者と課題意識を共有して一緒に取り組むという信頼関係をつくることや,訪問型支援による保護者への支援等,保護者が気軽に相談できる体制を整えることが重要であること。
2 学校等の取組の充実
(1)「児童生徒理解・支援シート」を活用した組織的・計画的支援
不登校児童生徒への効果的な支援については,学校及び教育支援センターなどの関係機関を中心として組織的・計画的に実施することが重要であり,また,個々の児童生徒ごとに不登校になったきっかけや継続理由を的確に把握し,その児童生徒に合った支援策を策定することが重要であること。その際,学級担任,養護教諭,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー等の学校関係者が中心となり,児童生徒や保護者と話し合うなどして,「児童生徒理解・支援シート(参考様式)」(別添1)(以下「シート」という。)を作成することが望ましいこと。これらの情報は関係者間で共有されて初めて支援の効果が期待できるものであり,必要に応じて,教育支援センター,医療機関,児童相談所等,関係者間での情報共有,小・中・高等学校間,転校先等との引継ぎが有効であるとともに,支援の進捗状況に応じて,定期的にシートの内容を見直すことが必要であること。また,校務効率化の観点からシートの作成に係る業務を効率化するとともに,引継ぎに当たって個人情報の取扱いに十分留意することが重要であること。
なお,シートの作成及び活用に当たっては,「児童生徒理解・支援シートの作成と活用について」(別添2)を参照すること。
(2)不登校が生じないような学校づくり
1.魅力あるよりよい学校づくり
児童生徒が不登校になってからの事後的な取組に先立ち,児童生徒が不登校にならない,魅力ある学校づくりを目指すことが重要であること。
2.いじめ,暴力行為等問題行動を許さない学校づくり
いじめや暴力行為を許さない学校づくり,問題行動へのき然とした対応が大切であること。また教職員による体罰や暴言等,不適切な言動や指導は許されず,教職員の不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は,懲戒処分も含めた厳正な対応が必要であること。
3.児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施
学業のつまずきから学校へ通うことが苦痛になる等,学業の不振が不登校のきっかけの一つとなっていることから,児童生徒が学習内容を確実に身に付けることができるよう,指導方法や指導体制を工夫改善し,個に応じた指導の充実を図ることが望まれること。
4.保護者・地域住民等の連携・協働体制の構築
社会総掛かりで児童生徒を育んでいくため,学校,家庭及び地域等との連携・協働体制を構築することが重要であること。
5.将来の社会的自立に向けた生活習慣づくり
児童生徒が将来の社会的自立に向けて,主体的に生活をコントロールする力を身に付けることができるよう,学校や地域における取組を推進することが重要であること。
(3)不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実
1.不登校に対する学校の基本姿勢
校長のリーダーシップの下,教員だけでなく,様々な専門スタッフと連携協力し,組織的な支援体制を整えることが必要であること。また,不登校児童生徒に対する適切な対応のために,各学校において中心的かつコーディネーター的な役割を果たす教員を明確に位置付けることが必要であること。
2.早期支援の重要性
不登校児童生徒の支援においては,予兆への対応を含めた初期段階からの組織的・計画的な支援が必要であること。
3.効果的な支援に不可欠なアセスメント
不登校の要因や背景を的確に把握するため,学級担任の視点のみならず,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー等によるアセスメント(見立て)が有効であること。また,アセスメントにより策定された支援計画を実施するに当たっては,学校,保護者及び関係機関等で支援計画を共有し,組織的・計画的な支援を行うことが重要であること。
4.スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携協力
学校においては,相談支援体制の両輪である,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーを効果的に活用し,学校全体の教育力の向上を図ることが重要であること。
5.家庭訪問を通じた児童生徒への積極的支援や家庭への適切な働き掛け
学校は,プライバシーに配慮しつつ,定期的に家庭訪問を実施して,児童生徒の理解に努める必要があること。また,家庭訪問を行う際は,常にその意図・目的,方法及び成果を検証し適切な家庭訪問を行う必要があること。
なお,家庭訪問や電話連絡を繰り返しても児童生徒の安否が確認できない等の場合は,直ちに市町村又は児童相談所への通告を行うほか,警察等に情報提供を行うなど,適切な対処が必要であること。
6.不登校児童生徒の学習状況の把握と学習の評価の工夫
不登校児童生徒が教育支援センターや民間施設等の学校外の施設において指導を受けている場合には,当該児童生徒が在籍する学校がその学習の状況等について把握することは,学習支援や進路指導を行う上で重要であること。学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合には,当該学習の評価を適切に行い指導要録に記入したり,また,評価の結果を通知表その他の方法により,児童生徒や保護者,当該施設に積極的に伝えたりすることは,児童生徒の学習意欲に応え,自立を支援する上で意義が大きいこと。
7.不登校児童生徒の登校に当たっての受入体制
不登校児童生徒が登校してきた場合は,温かい雰囲気で迎え入れられるよう配慮するとともに,保健室,相談室及び学校図書館等を活用しつつ,徐々に学校生活への適応を図っていけるような指導上の工夫が重要であること。
8.児童生徒の立場に立った柔軟な学級替えや転校等の対応
いじめが原因で不登校となっている場合等には,いじめを絶対に許さないき然とした対応をとることがまずもって大切であること。また,いじめられている児童生徒の緊急避難としての欠席が弾力的に認められてもよく,そのような場合には,その後の学習に支障がないよう配慮が求められること。そのほか,いじめられた児童生徒又はその保護者が希望する場合には,柔軟に学級替えや転校の措置を活用することが考えられること。
また,教員による体罰や暴言等,不適切な言動や指導が不登校の原因となっている場合は,不適切な言動や指導をめぐる問題の解決に真剣に取り組むとともに,保護者等の意向を踏まえ,十分な教育的配慮の上で学級替えを柔軟に認めるとともに,転校の相談に応じることが望まれること。
保護者等から学習の遅れに対する不安により,進級時の補充指導や進級や卒業の留保に関する要望がある場合には,補充指導等の実施に関して柔軟に対応するとともに,校長の責任において進級や卒業を留保するなどの措置をとるなど,適切に対応する必要があること。また,欠席日数が長期にわたる不登校児童生徒の進級や卒業に当たっては,あらかじめ保護者等の意向を確認するなどの配慮が重要であること。
(4)不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保
不登校児童生徒の一人一人の状況に応じて,教育支援センター,不登校特例校,フリースクールなどの民間施設,ICTを活用した学習支援など,多様な教育機会を確保する必要があること。また,夜間中学において,本人の希望を尊重した上での受入れも可能であること。
義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては,別記1によるものとし,高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において,指導・助言等を受けている場合の指導要録上の出席扱いについては,「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」(平成21年3月12日付け文部科学省初等中等教育局長通知)によるものとすること。また,義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱いについては,別記2によるものとすること。その際,不登校児童生徒の懸命の努力を学校として適切に判断すること。
なお,不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際には,「民間施設についてのガイドライン(試案)」(別添3)を参考として,判断を行う際の何らかの目安を設けておくことが望ましいこと。
また,体験活動においては,児童生徒の積極的態度の醸成や自己肯定感の向上等が期待されることから,青少年教育施設等の体験活動プログラムを積極的に活用することが有効であること。
(5)中学校等卒業後の支援
1.高等学校入学者選抜等の改善
高等学校入学者選抜について多様化が進む中,高等学校で学ぶ意欲や能力を有する不登校生徒について,これを適切に評価することが望まれること。
また,国の実施する中学校卒業程度認定試験の活用について,やむを得ない事情により不登校となっている生徒が在学中に受験できるよう,不登校生徒や保護者に対して適切な情報提供を行うことが重要であること。
2.高等学校等における長期欠席・中途退学への取組の充実
就労支援や教育的ニーズを踏まえた特色ある高等学校づくり等も含め,様々な取組や工夫が行われることが重要であること。
3.中学校等卒業後の就学・就労や「ひきこもり」への支援
中学校時に不登校であり,中学校卒業後に進学も就労もしていない者,高等学校へ進学したものの学校に通えない者,中途退学した者等に対しては,多様な進学や職業訓練等の機会等について相談できる窓口や社会的自立を支援するための受皿が必要であること。また,関係行政機関等が連携したり,情報提供を行うなど,社会とのつながりを絶やさないための適切な対応が必要であること。
4.改めて中学校等で学び直すことを希望する者への支援
不登校等によって実質的に義務教育を十分に受けられないまま中学校等を卒業した者のうち,改めて中学校等で学び直すことを希望する者については,「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について」(平成27年7月30日付け文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長通知)に基づき,一定の要件の下,夜間中学での受入れを可能とすることが適当であることから,夜間中学が設置されている地域においては,卒業時に夜間中学の意義や入学要件等について生徒及び保護者に説明しておくことが考えられること。
3 教育委員会の取組の充実
(1)不登校や長期欠席の早期把握と取組
教育委員会においては,学校等の不登校への取組に関する意識を更に高めるとともに,学校が家庭や関係機関等と効果的に連携を図り,不登校児童生徒に対する早期の支援を図るための体制の確立を支援することが重要であること。
(2)学校等の取組を支援するための教育条件等の整備等
1.教員の資質向上
教育委員会における教員の採用・研修を通じた資質向上のための取組は不登校への適切な対応に資する重要な取組であり,初任者研修を始めとする教職経験に応じた研修,生徒指導・教育相談といった専門的な研修,管理職や生徒指導主事を対象とする研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図り,不登校に関する知識や理解,児童生徒に対する理解,関連する分野の基礎的な知識などを身に付けさせていくことが必要であること。また,指導的な教員を対象にカウンセリングなどの専門的な能力の育成を図るとともに,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー等の専門性と連動した学校教育への更なる理解を図るといった観点からの研修も重要であること。
2.きめ細やかな指導のための適切な人的措置
不登校が生じないための魅力ある学校づくり,「心の居場所」としての学校づくりを進めるためには,児童生徒一人一人に対してきめ細やかな指導が可能となるよう,適切な教員配置を行うことが必要であること。また,異校種間の人事交流や兼務などを進めていくことも重要であること。
不登校児童生徒が多く在籍する学校については,教員の加配等,効果的かつ計画的な人的配置に努める必要があること。そのためにも日頃より各学校の実情を把握し,また加配等の措置をした後も,この措置が効果的に活用されているか等の検証を十分に行うこと。
3.保健室,相談室や学校図書館等の整備
養護教諭の果たす役割の大きさに鑑み,養護教諭の複数配置や研修機会の充実,保健室,相談室及び学校図書館等の環境整備,情報通信機器の整備等が重要であること。
4.転校のための柔軟な措置
いじめや教員による不適切な言動や指導等が不登校の原因となっている場合には,市区町村教育委員会においては,児童生徒又は保護者等が希望する場合,学校と連携した適切な教育的配慮の下に,就学すべき学校の指定変更や区域外就学を認めるなどといった対応も重要であること。また,他の児童生徒を不登校に至らせるような深刻ないじめや暴力行為があった場合は,必要に応じて出席停止措置を講じるなど,き然とした対応の必要があること。
5.義務教育学校設置等による学校段階間の接続の改善
義務教育学校等において9年間を見通した生徒指導の充実等により不登校を生じさせない取組を推進することが重要であること。また,小中一貫教育を通じて蓄積される優れた不登校への取組事例を広く普及させることが必要であること。
6.アセスメント実施のための体制づくり
不登校の要因・背景が多様・複雑化していることから,初期の段階での適切なアセスメントを行うことが極めて重要であること。そのためには,児童生徒の状態によって,専門家の協力を得る必要があり,スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置・派遣など学校をサポートしていく体制の検討が必要であること。
(3)教育支援センターの整備充実及び活用
1.教育支援センターを中核とした体制整備
今後,教育支援センターは通所希望者に対する支援だけでなく,これまでに蓄積された知見や技能を生かし,通所を希望しない者への訪問型支援,シートのコンサルテーションの担当など,不登校児童生徒への支援の中核となることが期待されること。
また,不登校児童生徒の無償の学習機会を確保し,不登校児童生徒への支援の中核的な役割を果たしていくため,未設置地域への教育支援センターの設置又はこれに代わる体制整備が望まれること。そのため,都道府県教育委員会は,域内の市区町村教育委員会と緊密な連携を図りつつ,未整備地域を解消して不登校児童生徒や保護者が利用しやすい環境づくりを進め,「教育支援センター整備指針(試案)」(別添4)を参考に,地域の実情に応じた指針を作成し必要な施策を講じていくことが求められること。
市区町村教育委員会においては,主体的に教育支援センターの整備充実を進めていくことが必要であり,教育支援センターの設置促進に当たっては,例えば,自治体が施設を設置し,民間の協力の下に運営する公民協営型の設置等も考えられること。もとより,市区町村教育委員会においても,「教育支援センター整備指針」を策定することも考えられること。その際には,教育支援センターの運営が不登校児童生徒及びその保護者等のニーズに沿ったものとなるよう留意すること。
なお,不登校児童生徒への支援の重要性に鑑み,私立学校等の児童生徒の場合でも,在籍校と連携の上,教育支援センターの利用を認めるなど柔軟な運用がなされることが望ましいこと。
2.教育支援センターを中核とした支援ネットワークの整備
教育委員会は,積極的に,福祉・保健・医療・労働部局等とのコーディネーターとしての役割を果たす必要があり,各学校が関係機関と連携しやすい体制を構築する必要があること。また,教育支援センター等が関係機関や民間施設等と連携し,不登校児童生徒やその保護者を支援するネットワークを整備することが必要であること。
(4)訪問型支援など保護者への支援の充実
教育委員会においては,保護者に対し,不登校のみならず子育てや家庭教育についての相談窓口を周知し,不登校への理解や不登校となった児童生徒への支援に関しての情報提供や相談対応を行うなど,保護者に寄り添った支援の充実が求められること。また,プライバシーに配慮しつつも,困難を抱えた家庭に対する訪問型支援を積極的に推進することが重要であること。
(5)民間施設との連携協力のための情報収集・提供等
不登校児童生徒への支援については,民間施設やNPO等においても様々な取組がなされており,学校,教育支援センター等の公的機関は,民間施設等の取組の自主性や成果を踏まえつつ,より積極的な連携を図っていくことが望ましいこと。そのために,教育委員会においては,日頃から積極的に情報交換や連携に努めること。
≪関係報告等≫
・「不登校児童生徒への支援に関する最終報告~一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進~」(平成28年7月 不登校に関する調査研究協力者会議)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/108/houkoku/1374848.htm
・「児童生徒の教育相談の充実について~学校の教育力を高める組織的な教育相談体制づくり~(報告)」(平成29年1月 教育相談等に関する調査研究協力者会議)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/066/gaiyou/1381049.htm
・「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実~個々の児童生徒の状況に応じた環境づくり~(報告)」(平成29年2月 フリースクール等に関する検討会議)
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/107/houkoku/1382197.htm
・「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 の施行状況に関する議論のとりまとめ」(令和元年6月 不登校に関する調査研究協力者会議,フリースクール等に関する検討会議,夜間中学設置推進・充実協議会)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1418510.htm
|
◆不登校2割増 最多29万人
小中、4割専門相談せず 朝日新聞2023(令和5)年10月4日
学校現場の様々な課題を把握するため、文部科学省が実施する「児童生徒の問題行動・不登校調査」の2022年度の結果が判明した。不登校の小中学生は過去最多の約29万9千人。前年度比22・1%の大幅増となった。うち学校内外の専門機関に相談していない児童生徒も過去最多の約11万4千人。いじめは小中高などで約68万2千件が認知され、被害が深刻な「重大事態」は923件。いずれも過去最多だった。
今回の結果を受け、文科省はこども家庭庁と連携して、不登校といじめ対策の「緊急加速プラン」を策定。一部は今年度中から実行に移す。例えば、不登校で学びにつながっていない子どもを支援する地域拠点の強化などを前倒しで行う。いじめの事態に至る共通要素を把握して、同省の重大事態対応ガイドラインの改定で対策強化を図る。
不登校の約4割にあたる11万4217人は養護教諭や教育支援センターなど学校内外の専門機関に相談していなかった。
朝日新聞 社説 2023.10.27
フリースクール 多様な学び当たり前に
学校に行けない、行かない小中学生が30万人もいる時代だ。学校の枠にしばられない多様な学びを選ぶことが、当たり前に認められなければ、教育を受ける権利が保障された国とはいえない。
そんな危機感を抱かせたのが、滋賀県東近江市長の乱暴な発言だった。「フリースクールは国家の根幹を崩しかねない」「善良な市民は、嫌がる子どもを学校に押し込んででも義務教育を受けさせようとしている」。小椋正清市長の発言は17日、不登校対策を議論する県の首長会議で出た。会議後には「不登校の大半は親の責任」とも語った。
撤回を求める意見が相次ぎ、市長は24日に「軽率な発言だった」と釈明した。
「多様で適切な学習活動」の重要性を明記した教育機会確保法が超党派の議員立法で成立してから7年。地方自治体の長が、法の趣旨をここまでないがしろにすることに驚く人も多いだろう。
法の施行後、フリースクールに通う子の授業料や交通費を補助する自治体は徐々に増え、独自の認証制度を設ける動きも出てきた。19年には文科省が通知で「学校に戻ること」を前提としない方針を打ち出し、籍を置く学校が「出席扱い」にしやすくなった。
一方、こうした学びが公教育の枠外にあり続けているのも事実だ。確保法の当初案には、一定の基準を満たせば義務教育として認める仕組みがあったが、「不登校を助長する」などの異論が出て削除された。結果、公的支援は乏しいままで、経営に苦しむ施設や、授業料負担のために諦める家庭も多い。不登校の子や親が相談に訪れる地域の教育支援センターに「パンフレットを置くことすらできない」という運営者の訴えも聞く。
学校以外の施設が存在感を増し、すでに学びの一翼を担っている現実と、教育制度の中で「隠れた存在」であることのギャップが、今回の発言の背景にある。利用者が増え続けるなかで、授業料などを補助する自治体の戸惑いも理解はできる。
異年齢の子が共に学ぶ、芸術活動を重視する、といった従来の学校にはない教育や国際的な学びへの関心も高まっている。多様な学びを公教育の中にどう位置づけるのか。どこまで認め、どう質を担保するのか。デメリットも含め、立法過程で積み残した議論を深める時期に来ているのではないか。
「嫌がる子を無理に押し込む」のではなく、子どもが安心して学べる環境を整えることが国や行政、大人に課せられた責務なのだから。
 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」
(平成二十八年法律第百五号)施行日: 令和五年四月一日(令和四年法律第七十六号による改正)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
 戻る 戻る
 教育を受ける権利の保障と教育の無償化について 教育を受ける権利の保障と教育の無償化について
 保育・幼児教育の意義と重要性 《現状の問題》 保育・幼児教育の意義と重要性 《現状の問題》
 教育を受ける権利と学歴偏重 教育を受ける権利と学歴偏重
 発達障害をどのように理解するか 発達障害をどのように理解するか
 発達障害と特別支援教育について 発達障害と特別支援教育について
 共生社会とインクルーシブ教育を考える 共生社会とインクルーシブ教育を考える
 大学の入試改革をめぐって 大学の入試改革をめぐって
 「9月入学」問題を考える 「9月入学」問題を考える
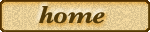
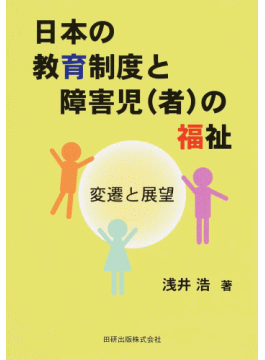
日本の障害児(者)の教育や福祉をめぐる問題、課題を考察し、今後を展望
田研出版 3190円 A5判 316頁
copyright ⓒ2012 日本の「教育と福祉」を考える all rights reserved
|