|
ノーマライゼーションと障害児者の教育と福祉
日本の障害児者の教育と福祉 特別支援教育について 障害者福祉の施策について 「完全参加と平等」について “新たな施設観”の構築 地域生活支援と「施設」の意義 “新たな施設観” の確立について 日本の障害児・者施設の原点
特別支援教育について
|
1960年代以降のノーマライゼーション理念の広がりと、1981(昭和56)年の国際障害者年を契機とする変化は、日本の障害者施設の在り方にも変化をもたらし、「施設から地域へ」「地域移行」というのが合い言葉のようになり、2026年度末までに施設入所者数の5%削減という数値目標も示されています。しかしそれが難しいという実情も踏まえた施策が必要であることも確かです。 これまでを振り返ってみたとき、日本ではノーマライゼーションやインクルーシブの理念が果たして本当に理解された上で広まってきたといえるかどうか、その点の丁寧な検証は今後の障害児者の教育や福祉の問題を考える上できわめて大切なことではないかと思います。 日本には日本の実情を踏まえた日本流の確たる取り組みがあってもよいはずですが、そうした理解の仕方や考え方が欠けていたように思います。 ノーマライゼーションの理念は、施設の整備を進める日本に混乱を招いた一方で、施設整備に関する反省すべき点について学び、考えることにもなったはずです。 施設中心の障害者支援から地域生活を支援する方向への転換はよいと思いますが、それがこれまでの「施設」の意義や必要性を否定するものならば、結果的には地域福祉や障害者福祉の推進や充実を図るための社会資源を否定することだと思います。 |
地域生活支援と「施設」の意義
障害のある人もない人も、人として生きる権利は同等です。したがって障害のある人が堂々と生活できるような施策を講じるのは社会的義務です。それは必然的にそのための社会環境を整備することであり、人々の理解が得られるものでなければなりません。
脱施設化政策により、障害のある人が地域社会の中で問題なく生活できればよいと思います。しかし脱施設後の生活を保障する基盤整備は不十分のままの現状があります。
障害の内容を改善し軽減することはできても、障害の程度や状態には大きな差があり多様です。しかもその差とはやがて追いつくとか治るというものではなく、質的な差異と考えたほうがよさそうです。
知的発達に障害のある場合、その障害特質としての主体性(自律性)の弱さや生活に必要な情報を得たり、生活に必要な技術を習得するのが苦手なことなどが問題となります。
そのため日常生活や社会生活に困難が生じるとすれば、長期的・継続的な支援を必要とします。そうした支援を考えたとき、そこに「施設」の意義と必要性を考えることができます。
“新たな施設観” の確立について
施設中心の障害者福祉から地域生活を支援する福祉施策を重視する方向への転換はよいと思います。しかし、それがこれまでの「施設」の意義や必要性を否定するものならば、結果的には地域福祉を充実させる社会資源を否定することだと思います。
施設の在り方で重要なことは、施設が社会的にどのように位置づけられ、人々の理解がどのように得られ、そこでどのようなことがどのように行われるかどうかだと思います。
今大切なことは、障害児・者の実態に即した日本流の体系的理念を確立することです。 そして安易な“収容施設”という非人間的な旧来のイメージは一掃し、“新たな施設観”を確立し、定着させることだと思います。
そのためには施設がこれまで果たしてきた役割や機能を改めて認識し直すとともに、障害児・者の“生涯”を見据えた福祉施策を担うことのできる人材を育成・確保することです。これは今の日本の重要課題だと思います。
これまでの施設における取り組みのすべてが否定されるようなものではなく、施設をよくないものとする見方は偏見や差別を助長するだけではないかと思います。障害者にかかわる施設整備はきわめて有効なものとして社会的に堂々と位置づけられてよいはずです。施設が地域社会の中にあって、そこが障害をもつ人の生活の拠点となるような社会的環境の整備の推進は日本の実情においては必要です。それは “新たな施設観” となって障害をもつ人の生活ニーズに対応し、施設の機能や役割の活性化と充実を促し、障害者福祉の向上に寄与するものと確信します。
日本の障害児・者施設の原点
日本の障害児(者)施設の原点は、石井亮一が創設した「滝乃川学園」にあるといってよいと思います。その取り組みは、学校教育という公教育的立場のものとは対照的な社会福祉的立場に立ったものであり、それはまた社会防衛的な発想に基づく欧米の施設とも対照的な、社会の厳しい状況から障害児を守ろうという人道的発想に基づくものです。
その取り組みは、単に施設に隔離し、保護するというのではなく、生活能力を高めようとする教育的取り組みであったというところに大きな意味があるわけです。
ノーマライゼーションの理念は、施設の整備を推進する日本に混乱を招きましたが、その一方で施設の整備を進める上で反省すべき点について考える機会を得たことにもなります。その反省点を踏まえつつ日本の施設福祉の充実を図ることこそが実態に即していると考えます。混迷したときに、原点に立ち戻って考え直してみることの大切さを忘れてはならないと思います。
日本の教育や福祉は今、大きな変革期の中にあり、混迷した状況が見られます。日本の知的障害に関する教育や福祉の原点ともいえる滝乃川学園の創設者である石井亮一(1867~1937年)や、戦後では、近江学園の創設者である糸賀一雄(1914~1968年)や旭出学園の創設者である三木安正(1911~1984年)の思想や取り組みをあらためてたどってみることの意義は大きいと思います。そこには目指すべき考え方の拠りどころとなるものがあるはずです。 ⇒ |
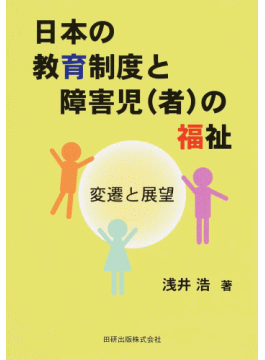
日本の障害児(者)の教育や福祉をめぐる問題、課題を考察し、今後を展望
田研出版 3190円 A5判 316頁
第1章 日本の障害児教育の始まりと福祉
義務教育の制度と障害児/学校教育と福祉施設/精神薄弱者福祉法(現:知的障害者福祉法)の制定/教育を受ける権利の保障
第2章 戦後の復興から社会福祉基礎構造改革へ
社会福祉法人制度と措置委託制度/社会の変化と社会福祉基礎構造改革/「措置」から「契約」への制度転換と問題点
/社会福祉法人制度改革の意義と課題
第3章 障害者自立支援法から障害者総合支援法へ
障害者自立支援法のねらい/障害者自立支援法をめぐる問題/自立支援法から総合支援法へ/障害者総合支援法施行3年後の見直し
第4章 教育の意義と福祉の意義
人間的成長発達の特質と教育・福祉/人間的進化と発達の個人差/教育と福祉の関係/「福祉」の意味と人権
第5章 展望所感
障害(者)観と用語の問題/新たな障害(者)観と国際生活機能分類の意義/障害児教育の義務制の意義と課題/障害者支援をめぐる問題
copyright ⓒ2012 日本の「教育と福祉」を考える all rights reserved.
